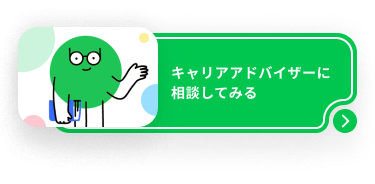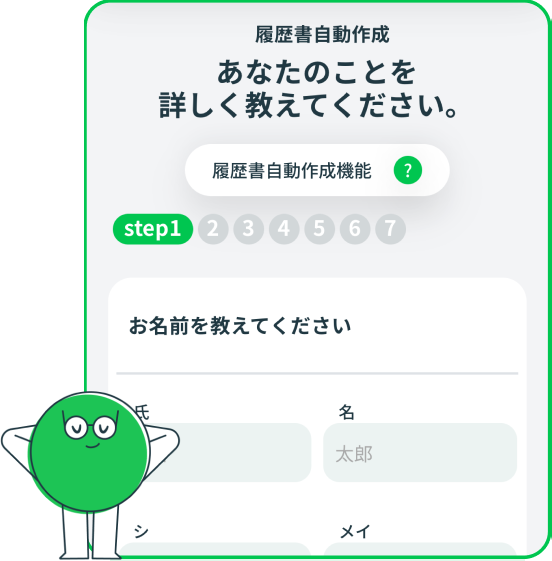円満退社するために交渉は必須! 引き留めにあった際の対策も解説
転職先から内定が出たら、次は現在の勤務先での退職手続きです。引き留めや退職日の調整など、退職交渉は面倒で気が重いと感じがちです。
円満に退職するためには、退職交渉に臨む姿勢やポイントがあります。この記事では、退職交渉の背景や、スムーズに進めるための次のようなポイントを解説します。
●企業が引き留めてくる理由は、人材として評価している、人手不足で困る、会社のせいにされたくないことが挙げられる
● 退職の意思を伝えるときは、内定後できるだけ早く直属の上司に伝える
●いろいろな引き留めがありうるが、交渉では退職を決定事項として一貫した態度を取ることが大切
●難航させないためには、ブレずに一貫した態度を持ちつつ妥協できるところは妥協するとよい
この記事は、順を追って読んだ方が理解しやすい流れになっていますが、気になるところだけを拾い読みしても参考になる内容になっています。
まず退職時に引き留めにあう理由を確認

企業が退職希望者を引き留めるのは、次のような理由からです。
・人材として高く評価している
・人材不足で辞められると困る
・会社のせいにされるのが怖い
上記について、それぞれ見ていきます。
人材として高く評価している
企業側は、まず、業務遂行能力の高い従業員の離職を防ぎたいという理由から、退職を思いとどまるよう引き留めます。
職場でリーダーシップを発揮している人材が抜けると、組織の安定性に影響を与えるので、引き留めの対象になりやすい傾向にあります。
評価の高い人材が退職すると、ドミノ倒しのように離職が続く場合が少なくありません。
また、特定の人に依存しがちな業務が多い、業務が属人化している場合には、引き継ぎの負担を理由に退職を思いとどまらせようとすることもあります。
人材不足で辞められると困る
慢性的な人材不足に直面している企業は、退職者が出ると業務に支障をきたすという理由で、多くの場合、退職希望者を引き留めます。
専門職や経験豊富な従業員が退職する際には、人材の育成や確保が難しいので、引き留めが強くなる傾向にあります。
また、求人募集や採用活動には時間とコストがかかるため、新たな人材を確保するまでの負担を避けたいのも、企業が退職者を引き留める理由の一つです。
会社のせいにされるのが怖い
従業員の退職理由が、会社の労働環境や待遇の問題にされることを避けたくて、引き留めを行うことがあります。
退職者が増えると社内の士気が下がり、他の従業員にも影響を与えるため、退職者が増えることも企業が避けたいリスクです。
また、企業の評判が悪化すると、採用活動や取引先との関係に影響を及ぼすおそれがあるため、退職理由の公表を避ける目的で引き留めることもあります。
転職に伴う退職を伝える際のやるべきこと
転職を機に退職する際に確認しておくこと、するべきことをまとめたので、参考にしてください。
・就業規則でいつまでに意思表示すればいいかを確認する
・内定後、早めに直属の上司に口頭で伝える
・伝えるその日中に時間をもらう
・報告であることを意識して臨む
・人ではなく組織に引き継ぎする意識を持つ
・退職日や有給休暇の取得を決定して退職届を出す
・貸与品などを返却する
上記について、一つずつ見ていきます。
就業規則でいつまでに意思表示すればいいかを確認する
退職の申し出期限は企業によって異なるため、事前に就業規則を確認し、適切なタイミングを把握しておくことが大切です。
一般的には「退職希望日の1カ月前まで」に申し出るケースが多いのですが、役職や職種によっては、より早めの意思表示が求められることもあります。
引き継ぎに時間がかかる業務を担当している場合や、会社の繁忙期と重なる場合は、早めに相談することで円滑に進めやすくなります。
期限を守らず急に退職を申し出ると印象が良くないだけでなく、引き継ぎが進まず、円満に退社するのが難しくなる可能性があるので注意が必要です。
内定後、早めに直属の上司に口頭で伝える
退職の意思は、内定を得た後できるだけ早く、直属の上司に口頭で伝えるのが望ましいとされています。
直接伝えることで誠意が伝わり、円満な退社につながります。伝えるタイミングが遅れると、引き継ぎの負担が増える、企業側からの引き留めが強まるなどのデメリットが発生します。
スムーズな退職のためにも、適切なタイミングで上司に相談し、早めに準備を進めることが大切です。
伝えるその日中に時間をもらう
退職の意思を伝える際は、当日中に上司と話す時間を確保し、速やかに報告することが大切です。
事前に「お時間をいただけますか」と依頼し、落ち着いて話せる状況を作ることが、円滑な退職交渉につながります。
時間を確保せずに突然切り出すと、上司が多忙で十分な話し合いができず、退職の意思が正しく伝わらない可能性があるため注意が必要です。
報告であることを意識して臨む
退職の意思を伝える際は、「相談」ではなく「報告」であることを意識し、決定事項として伝えることが大切です。
「退職を考えている」というように、あいまいな言い方で伝えると、上司が引き留める余地があると判断して、話が長引く可能性があります。「退職することを決めました」と明確に伝えた方が、不要な交渉を避けやすくなります。
また、上司によっては受け取り方が違うので、言葉や伝え方を選ぶことも重要です。強い口調で一方的に伝えるのではなく、感謝の気持ちを添えながら冷静に報告して、円満な退職につながるようにします。
人ではなく組織に引き継ぎする意識を持つ
引き継ぎは特定の個人だけでなく、組織全体に対して行う意識を持つことが大切です。業務が属人化していると、後任者の負担が増え、スムーズな引き継ぎが難しくなります。
業務マニュアルを作成し、誰でも対応できる形にすることが有効です。手順や注意点を整理して、必要な情報を共有できると引き継ぎの効率が上がります。
退職後も業務が滞りなく進むよう配慮すると、円満な退社につながります。将来また関わる可能性もあるので、退職後も関係を良好に保っておくのが、自分にとってプラスにつながります。
退職日や有給休暇の取得を決定して退職届を出す
退職を円滑に進めるには、退職日や有給休暇の取得予定を事前に決め、計画的に手続きを進めることが大切です。スケジュールを明確にしておくと、引き継ぎの調整もしやすくなります。
退職届は、会社の規定に従い、まず上司に報告したう上で正式な書類を提出するのが基本的な手順です。適切に進めることで、不要なトラブルを防ぐことができます。
また、有給休暇の取得については、会社の方針や業務の状況を考慮しながら、周囲と調整することが重要です。事前に相談して計画的に進めると、スムーズに退職日を迎えられるでしょう。
貸与品などを返却する
退職時には、会社から貸与されたPCやスマートフォン、社員証などを漏れなく返却することが大切です。返却漏れがあると、後から連絡が来るなどのトラブルにつながる可能性があります。
スムーズに手続きを進めるためには、返却リストを作成し、上司や総務と確認しながら進めると安心です。事前にチェックしておくことで、手続きの抜け漏れを防ぐことができます。
また、データの取り扱いにも注意が必要です。会社の情報が私物のデバイスに残らないよう、適切に処理し、社内規定に沿って対応しましょう。
退職交渉のタイミング

退職交渉のタイミングについて、知っておきたい前提と適切なタイミングを紹介します。
・タイミングに関わる二つの前提
・中長期で見たタイミング:繁忙期を避ける
・短期的なタイミング:上司のスケジュールに配慮する
上記のポイントについて、それぞれ見ていきます。
タイミングに関わる二つの前提
退職を決める際は、できるだけ事前に転職先を見つけておくことをおすすめします。収入の空白期間をなくし、経済的な不安を減らしましょう。
空白期間がない方が、その後の転職活動や新しい環境への移行もスムーズです。
また、円満退社のためには就業規則を確認し、定められた退職の申告期限を守ることが大切です。多くの企業では1~2カ月前の申告が求められますので、事前にチェックしておきましょう。
なお、法律上は退職の2週間前までに伝えれば問題ありません。ただし、職場への影響や自身の評価を考えると、できるだけ余裕のある行動を取るようにしましょう。
中長期で見たタイミング:繁忙期を避ける
退職のタイミングは繁忙期を避けるのが賢明です。忙しい時期の退職は、職場の同僚に業務負担が重くなり迷惑をかけることになるので、円満退社が難しくなりがちです。また、繁忙期は引き留めにあう確率も高くなります。
業種によって異なりますが、年度末や決算期は多くの職場で忙しくなるため、この時期の退職は避けた方がよいでしょう。
転職活動の段階から退職時期を意識し、スムーズに進められるよう計画することが大切です。
短期的なタイミング:上司のスケジュールに配慮する
退職の意思は、前述の通り、内定後できるだけ早く直属の上司に伝えるのが理想です。早めに報告できれば、引き継ぎや業務調整がスムーズに進み、周囲に負担をかけることも減るでしょう。
ただし、大きな商談の準備中や、上司が忙しい時間帯は、避けた方がよいタイミングです。そうした状況で話を切り出すと、上司に十分に聞いてもらえず、スムーズに進まない可能性があります。できれば事前に上司の時間を確保し、落ち着いて話せる状況を作りましょう。
また、退職の意思を伝える際は、感謝の気持ちを忘れず、今後の業務への影響を最小限にする姿勢を示すことも大切です。
退職交渉でよくある引き留めパターンと対処法

退職交渉の際には、よくある引き留めパターンがあります。それぞれの場合に適した対処法を紹介します。
・仕事やプロジェクトの完了や後任を待ってほしいと言われた場合
・待遇を改善すると言われた場合
・その他上司や同僚からの引き留めにあった場合
・話が平行線の場合は持ち帰るのもあり
上記について、それぞれ見ていきます。
仕事やプロジェクトの完了や後任を待ってほしいと言われた場合
退職の意思を伝えた後、仕事の完了や後任が決まるまで待つよう求められることが、よくあります。しかし、「◯月◯日で退職することは決定事項です」とはっきり伝え、意思を貫くことが重要です。曖昧な返答をすると、退職時期を引き延ばされる可能性があります。
円満に退職するためには、引き継ぎ計画を立てて、上司や後任者と共有しておくことが効果的です。「いつまでに何を引き継ぐか」を明確に示せば、スムーズに進めやすくなります。
また、会社の都合で退職を遅らせられないよう、就業規則を確認し、退職希望日の○日前までに退職届を提出しましょう。正式な手続きを踏むことで、計画通りの退職が可能になります。
待遇を改善すると言われた場合
退職の意思を伝えた際、給与や役職の引き上げを提示されることがあります。しかし、これらは一時的な引き留め策である可能性が高いため、揺らがないよう注意が必要です。
引き留めを受けても、「すでに次の会社と契約が決まっているため、お気持ちはありがたいですが退職の意思は変わりません」と冷静に伝えましょう。感情的にならず、毅然(きぜん)とした態度を取ることが大切です。
また、退職理由を聞かれた際に現職への不満を挙げると、引き留めを受けやすくなります。「新しい環境で挑戦したい」「キャリアの幅を広げたい」など、前向きな理由を伝える方がスムーズに進みます。
一度引き留めを受け入れると、将来的に再び退職を考えた際も同じように引き留められる可能性があります。退職の決断は、大きな決断なので慎重に考えて、そして揺るがずに進めることが大切です。
その他上司や同僚からの引き留めにあった場合
退職を伝えた後、直属以外の上司や同僚から引き留められることがあります。その際は、感情的にならず、一貫した態度を貫くのが適切です。
「決定事項であり、すでに次のステップに進む準備をしています」と明確に伝えると、不要な交渉を避けやすくなります。曖昧な返答をすると、引き留めが長引く原因になるため、はっきりと意思を示しましょう。
また、「チームが困る」「もう少し一緒に働いてほしい」といった同情を誘う説得もあるかもしれません。しかし、退職は個人のキャリアや健康に関わる決断です。罪悪感を抱かず、冷静に対応することが大切です。
話が平行線の場合は持ち帰るのもあり
退職の話し合いが平行線になった場合、その場で無理に結論を出そうとせず、「一度持ち帰ります」と伝えるのも、一つの方法です。即答を避け、お互いに冷静になって考えることができます。
感情的なやりとりを防ぐためにも、改めて上司と話す機会を設けると、交渉がスムーズに進む可能性があります。ただし、持ち帰った後も退職の意思が揺らがないよう、一貫した対応を心がけることが大切です。
また、交渉のタイミングを工夫するのも効果的です。休み直前の週末に話を持ちかけると、冷却期間が生まれ、落ち着いて判断しやすくなります。
退職交渉が難航する、やってはいけないこと

退職交渉において、交渉の難航につながるNGな対応があります。これらを事前にチェックして、役立ててください。
・転職先の都合だけで入社日を決めてしまう
・転職先の会社名を言う
・退職交渉を上司や第三者に委ねる
・有給消化やボーナスなどの待遇にこだわりすぎる
・留意条件を聞いてブレる
・現職に対する不満や愚痴を言う
・人間関係を悪化させる
・退職の意思を曖昧な表現で伝える
上記について、一つずつ見ていきます。
転職先の都合だけで入社日を決めてしまう
退職日を決める際は、転職先の都合に流されず、自分の意思を持つことが重要です。「転職先と相談中です」などの曖昧な表現をすると、交渉が長引き、企業側に引き留められる可能性が高まります。
スムーズに退職するためには、退職日を明確に設定し、「◯月◯日が最終出社日です」と具体的に伝えましょう。はっきりとした意思表示をすることで、不要な交渉を避けましょう。
転職先の会社名を言う
退職交渉の際、転職先の会社名を伝える必要はありません。聞かれても、「回答は控えさせていただきます」と対応しましょう。
会社名を伝えると、業界内の関係性によって妨害を受けたり、不本意な形で情報が広まったりするリスクがあります。不要なトラブルを避けるためにも、詳細を伝えないことが賢明です。
また、退職の理由や転職先について尋ねられた場合は、「新たな環境で挑戦したい」といった一般的な回答にとどめることで、余計な詮索を防ぎ、円満に退職しやすくなります。
退職交渉を上司や第三者に委ねる
退職交渉は、自分自身で行い、上司や第三者に任せないようにします。人任せにすると、意図が正しく伝わらず、交渉が長引いたり、不本意な条件を提示されたりする可能性があります。退職交渉には、人事部門も関わることが一般的です。人事部門とも直接、交渉してください。
円満に退職するためには、自分の言葉で退職の意思を明確に伝えることが大切です。「◯月◯日をもって退職します」と具体的かつ簡潔に伝えて不要な誤解を防ぎましょう。
有給消化やボーナスなどの待遇にこだわりすぎる
退職時の有給消化やボーナスの受給に固執しすぎると、交渉が長引き、円満退社が難しくなる可能性があります。会社の規定や状況によっては、有給消化が認められず、ボーナスの支給対象から外れることもあるため、事前に規定を十分に確認し、柔軟に対応することが大切です。
退職の本来の目的は、新しい環境でのスタートを切ることです。条件面にこだわりすぎず、スムーズに退職できることを優先するのが望ましいでしょう。
留意条件を聞いてブレる
退職交渉では、上司から「この条件なら残れるか?」と問われても、退職の意思を貫く姿勢が求められます。条件交渉に応じると、退職の決意が揺らいでいると判断され、引き留めが長引く可能性があります。
スムーズに退職するには、「すでに決定したことなので、お気持ちはありがたいですが退職します」と、一貫した態度で対応することが大切です。迷いを見せず、冷静に伝えると交渉が長引かずにすみます。
現職に対する不満や愚痴を言う
退職交渉では、現職への愚痴を口にすると、感情的な対立を招き、円満に退職しにくくなります。会社や上司への批判は控え、「新たな挑戦をしたい」「キャリアの幅を広げるため」といった前向きな理由を伝えるのが適切です。
また、退職後も業界内で関わる可能性があるため、最後まで礼儀正しく対応することが大切です。感謝の気持ちを示しつつ、冷静に話を進めることで、良好な関係を保つように努めます。
さらに、不満を理由にすると「改善するから残ってほしい」と引き留めにあうケースも少なくありません。交渉が長引く原因にもなるので、退職の理由は慎重に伝えるよう意識しましょう。
人間関係を悪化させる
退職交渉では、感情的にならず、冷静かつ誠実に対応することが大切です。落ち着いて話を進めることで、不要な対立を避け、人間関係を悪化させずにすむでしょう。
これまでにも述べた通り、上司や同僚には感謝の気持ちを伝え、円満な関係を維持することを忘れないようにします。
退職後のキャリアにも良い影響を与える可能性がありますし、少なくとも余計なトラブルを避けられます。
さらに、退職を決めた後も、引き継ぎや業務に責任を持って取り組むことが重要です。最後まで誠実に対応すると、すっきりとした気持ちで退職できます。
退職の意思を曖昧な表現で伝える
退職の意思を曖昧に伝えると、上司に引き留めの余地があると受け取られ、交渉が長引く原因になります。退職の話を進める際は、自分の意思を明確に示し、迷いがないことを伝えます。
再三お伝えしているように、「退職を考えています」ではなく、「◯月◯日をもって退職します」とはっきり伝えることが大切です。
交渉の会話が込み入った場合に、「まだ決めかねています」「もう少し検討したい」といった言葉を使うと、引き留めが続くので注意します。
言葉を濁さず、決定事項として伝えつつ、最後まで誠実に対応することで、余計なトラブルを避け、スムーズな退職につながるでしょう。
退職交渉が進まなくなった場合の対処法

退職交渉がうまく進まないこともときにはあります。そういった場合の対処法を紹介します。
・引き継ぎが順調に進まない場合
・強引な引き留めにあった場合
・大前提として時間がかかる意識を
上記について、一つずつ見ていきます。
引き継ぎが順調に進まない場合
引き継ぎが遅れる可能性がある場合でも、事前に業務マニュアルを作成し、誰でも対応できる状態にしておきます。急な対応が必要になった際も、業務が滞ることがないでしょう。また、上司や後任者とスケジュールを共有し、「◯日までに完了する」と期限を明確にすることで、引き継ぎが円滑に進みます。
さらに、退職日が決まっていることを前提に進め、「引き継ぎが終わらないから退職を延期する」という事態にならないようにします。
強引な引き留めにあった場合
退職の意思を何度も否定されたり、高圧的な態度で引き留められたりしても、冷静に対応する姿勢が必要です。感情的にならず、淡々と対応することで、不必要な対立を避けられます。
「すでに決定したことですので、変更はありません」と明確に伝えて、感情的な議論には巻き込まれないよう注意しましょう。相手の反応に揺さぶられることなく、落ち着いて対応を心がけます。
さらに、引き留めが度を超えて退職の妨害となる場合は、労働基準監督署や外部の専門機関に相談することも有効です。必要に応じて第三者の介入を検討し、適切な手続きを進めましょう。
大前提として時間がかかる意識を
退職交渉は一度で終わるとは限らず、複数回の話し合いが必要になることを前提に進めることが大切です。会社側も引き継ぎや後任の確保を考慮するため、一定の時間がかかることを理解し、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
また、焦って交渉を進めると、不利な条件を受け入れてしまう可能性があります。状況に流されないよう、冷静に対応しながら着実に進めるのがコツです。
転職の退職交渉が不安ならジョバディに相談!

今回は、退職交渉のタイミングや引き留め対策について紹介しました。
転職を考えているものの、退職交渉に不安を感じている方はジョバディにご相談ください。円満に退職するための引き継ぎや交渉の進め方について、具体的なアドバイスを提供します。
ジョバディでは、あなたのスキルや希望に合った求人紹介はもちろん、キャリア相談や条件交渉、面接対策など、多岐にわたるサポートを行っています。一人で悩まず、専門のアドバイザーとともに、理想のキャリアを実現しましょう。
まずは、無料登録からスタートしてみてください。