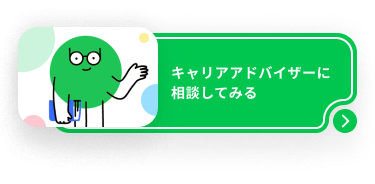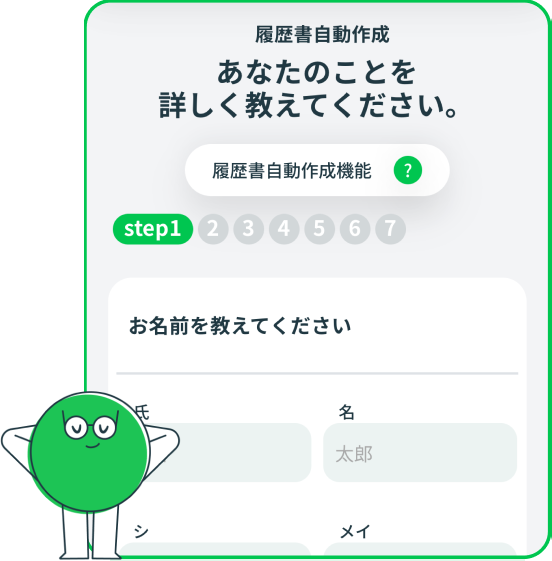仕事を休む理由の伝え方|注意点、理由なく休みたいときの対処法を解説!
「仕事を休みたい日」は、誰にでもあるものです。しかし、休む理由をどう伝えればよいのか、職場に迷惑をかけないかと考えてしまいます。
休みを取るときには理由を明確にして、周囲への影響を最小限に抑える工夫をしておくと、安心して休めます。
また、特に理由がなくても休みたいときには、有給休暇の活用や働き方改革の推進で、無理なく休める方法を見つけることができます。
本記事では、適切な休みの理由や伝え方、無理せず休むための工夫について解説します。次のような内容を紹介していますので、参考にしてください。
●仕事を休む際は、体調不良や家庭の事情など具体的な理由を考えた上で、職場の理解を得やすい適切な伝え方を工夫することが大切。連絡手段やタイミングを考え、業務への影響を最小限に抑える配慮も求められる。
●曖昧な理由やうその理由を使って仕事を休むと、上司や同僚からの信頼を損なう可能性があるため注意が必要。頻繁に同じ理由を使わないことや、休んだ後の対応をしっかり行うことが重要になる。
●理由がなくても、心身のリフレッシュやモチベーションの維持のために休みを取ることは問題ない。有給休暇を計画的に活用し、ストレスを軽減することで、長期的な業務のパフォーマンス向上につながる。
●どの方法を試しても仕事を続けるのがつらい場合は、上司や専門機関に相談し、休職や転職を視野に入れることも検討する。無理に働き続けると心身の健康を損なう恐れがあるため、適切なタイミングで判断することが大切。
この記事では、上記のそれぞれについて詳しく解説します。
順を追って読んだ方が理解しやすい流れになっていますが、気になるところだけを拾い読みしても参考になる内容になっています。
仕事を休みたいときの理由

仕事をしていると、体調不良や家庭の事情などで、当日になって休まなくてはならない場合があります。
そのような場合、適切に理由を伝えることで、当日の連絡でもスムーズに休暇を取得しやすくなります。急な体調不良の場合には、早めに上司や同僚に連絡して業務の調整をします。
また、ストレスや精神的な負担が原因で休みたいときは、無理をせず適切に対応するようにします。短期間の休息でも、気分が変わって仕事の効率も上がるでしょう。
さらに、モチベーションの低下や人間関係の悩みも、休みたい理由の一つです。この場合には、一時的に休むだけでなく、根本的な原因を見直し、解決策を考えることが重要です。
休む理由を具体化することが大事
当日に仕事を休むときに、上司や同僚の理解を得るためには、理由を分かりやすく具体的に伝えることが大切です。曖昧な表現を避け、状況をはっきり説明すれば不要な誤解を生むこともありません
「体調不良」とだけ伝えるよりも、「発熱があり外出が難しい」と伝えた方が、相手に状況が伝わります。
また、「家庭の事情」と漠然と言うのではなく、「親の介護で病院に同行する」など具体的に伝えると、休まなくてはならない事情を理解してもらえます。
つらいときでも理由は考えておくこと
精神的につらくて仕事を休みたいときには、適切に理由を伝えて休暇を取得します。
「体調不良」「通院」「家庭の事情」など、自分にとって無理のない範囲で伝えやすい理由を考えておくと、余計なストレスを感じずに済みます。詳細な説明は不要ですが、曖昧すぎると誤解を招くので、簡潔かつ納得しやすい理由を伝えることが大切です。
また、突然の休みに備え、普段から上司や同僚と良好な関係を築き、適切な報連相を行うことも重要です。信頼関係があると、急な休みでも悪い印象を与えないものです。
当日に仕事を休むと伝える場合の理由と例文

当日に仕事を休むと伝える際の理由と例文をケースごとにまとめましたので、参考にしてください。
・腹痛や下痢・吐き気などの体調不良
・インフルエンザやコロナなどの感染症
・腰痛やぎっくり腰などの持病
・虫歯などの歯痛
・体調不良や気圧による頭痛
・発熱
・生理痛
・通院や病院を受診する
・子どもや家族の体調不良
・貴重品の紛失などのトラブル
・交通事故などのトラブル
・車が動かないなどのトラブル
上記について、一つずつ紹介します。
腹痛や下痢・吐き気などの体調不良
腹痛や下痢、吐き気などの体調不良の場合は、「朝から体調が悪い」と伝えるだけでなく、「激しい腹痛が続いている」「吐き気があり業務が難しい」のように具体的に伝えると、仮病ではといった余計な詮索を避けられます。
また、症状が重い場合は無理をせず、必要に応じて病院を受診し、翌日以降の体調を考慮した対応を取るようにします。適切に休息を取り、回復してから業務に戻りましょう。
【例文】
おはようございます。今朝から激しい腹痛と吐き気があり、業務を行うのが難しいため、本日お休みをいただきます。症状が続く場合は病院を受診し、明日以降の勤務についても体調を見て判断します。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
インフルエンザやコロナなどの感染症
インフルエンザやコロナなどの感染症にかかった場合、職場への影響を考え、速やかに休む判断が必要です。「発熱があり医師から自宅療養を指示された」「コロナの陽性反応が出たため出社できない」と具体的に伝えます。
また、復帰のタイミングは医師の指示を確認し、熱が下がった後も無理せずに体調を見ながら調整します。感染症は、ほかの人にうつさないよう適切な対応を心がけ、職場への負担を最小限に抑えましょう。
【例文】
おはようございます。昨夜から高熱が続き、今朝病院を受診したところ、インフルエンザ(またはコロナ)の陽性と診断されました。医師から◯日間の自宅療養を指示されており、その間は出社が難しい状況です。
熱が下がって、体調を見ながら業務復帰したいと思います。ご迷惑をおかけしますが、なにとぞよろしくお願いいたします。
腰痛やぎっくり腰などの持病
腰痛やぎっくり腰は突然悪化します。無理に出社すると症状がひどくなって、長期間業務に支障をきたす恐れがあります。「腰の痛みが強く、動くのが困難なため自宅で安静にする」「ぎっくり腰で歩行が難しいため病院を受診する」と明確な症状を伝えます。また、早期に回復するよう努力していることが伝わるようにします。
また、慢性的な腰痛がある場合は、普段から上司や同僚に状況を共有し、休む際の業務調整を円滑に進められるよう備えておくことも大切です。
【例文】
おはようございます。今朝から腰の痛みが強く、動くのが困難なため、本日は自宅で安静にします。
ぎっくり腰の可能性があるため、症状が改善しない場合は病院を受診し、明日以降の勤務についても体調を見て判断します。できるだけ早く回復するよう、医師に相談して対処いたします。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
虫歯などの歯痛
虫歯や歯痛が悪化すると集中力が低下し、業務に支障をきたすことがあります。早めに治療を受けるため、必要に応じて半日または数時間の休みを取るのが適切です。「歯の痛みが強く、歯科を受診するため午後休みをいただきます」と伝えれば、スムーズに調整できます。
一方、親知らずの抜歯後は腫れや痛みが数日続くことがあり、発熱を伴う場合もあるため、事前に休みを申請し、無理のないスケジュールを組んでおくことが望ましいです。
【虫歯の場合の例文】
おはようございます。歯の痛みが強く、本日午前中に歯科を受診するため、半日休みをいただきます。治療後の状況を見て、午後から出社する予定です。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
【親知らず抜歯の場合の例文】
おはようございます。明日、親知らずの抜歯を予定しており、術後の腫れや痛みが続く可能性があるため、◯日まで休みをいただきます。経過を見ながら、回復次第業務に復帰します。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
体調不良や気圧による頭痛
頭痛や片頭痛が悪化すると集中力が低下し、業務に支障をきたすので、無理はしないようにします。「強い頭痛が続いており、業務が難しいため休養する」「片頭痛が悪化し、出社が困難な状況」と具体的な症状と休むことを伝えます。
また、慢性的に片頭痛がある場合は、日頃から上司や同僚に状況を伝えておきます。業務内容についても、同僚が見て分かるように整理しておきます。
【例文】
おはようございます。今朝から強い頭痛が続いており、業務に集中できないため、本日は休みを取らせていただきます。片頭痛が悪化していて、安静が必要な状態です。明日以降の勤務については、体調を見ながら判断します。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
発熱
発熱がある状態で無理に出社すると、症状が悪化したり、同僚に感染を広げたりするリスクがあります。速やかに発熱外来を受診し、感染症かどうか確認します。
会社には「朝から38度の発熱があり、体調が優れないため発熱外来を受診する」「高熱で業務に集中できず、感染症の検査を受ける必要がある」と具体的に伝えます。また、発熱が続く場合は、医師の診断を受け、必要に応じて翌日以降の出社可否について上司に相談するようにします。
【例文】
おはようございます。今朝から38度の発熱があり、体調が優れないため、本日は休養し、速やかに発熱外来を受診します。感染症の可能性もあるので、検査の結果に応じて明日以降の出社について改めてご連絡いたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
生理痛
生理痛が重いと、業務に集中できず体調が悪化することもあります。無理をせずに休む判断が必要です。
「腹痛や頭痛が強く、業務に支障をきたすため休養する」「生理痛がひどく立ち上がるのもつらいため、自宅で安静にする」と伝えて理解を得るようにしましょう。
また、症状が毎月続く場合は、事前に上司や人事に相談し、テレワークの活用や柔軟な働き方を検討するのも有効です。
【例文】
おはようございます。今朝から生理痛がひどく、腹痛と頭痛が強いため、本日は自宅で休養させていただきます。症状が落ち着き次第、業務に復帰する予定ですが、体調を見ながら判断いたします。急なご連絡となり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
通院や病院を受診する
定期的な通院や急な体調不良による病院受診は、仕事を休む理由として認められるものです。「持病の診察のため病院を受診する」「急な体調不良で医師の診察が必要なため休む」と簡潔に伝えれば、スムーズに調整しやすくなります。
また、事前に通院の予定が分かっている場合は、早めに上司へ報告し、業務の調整をしておくことが望ましいです。
【例文】
おはようございます。本日は持病の診察のため、午前中に病院を受診します。診察が終わり次第、午後から出社する予定ですが、状況によっては改めてご連絡いたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
子どもや家族の体調不良

子どもや家族の体調不良で看病や病院の付き添いが必要な場合にも、仕事を休むことができます。「子どもが高熱を出し、病院に連れて行く」「親の体調が悪く、介護対応が必要」と伝えると、調整がスムーズです。
また、急な休みに備え、日頃から上司や同僚と連携し、業務の引き継ぎ体制を整えておくと安心です。
【例文】
おはようございます。子どもが高熱を出し、病院に連れて行くため、本日はお休みをいただきます。病状次第では、明日以降の勤務についても調整が必要になるかもしれません。その際は改めてご連絡いたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
貴重品の紛失などのトラブル
財布や鍵、スマートフォンなどの貴重品を紛失した場合、再発行手続きや警察への届け出が必要となり、そのために仕事を休まざるを得ないことがあります。
「財布を落とし、警察への届け出と再発行手続きが必要なため休む」や「自宅の鍵を紛失したため、鍵の交換や住居のセキュリティ確認に立ち会う」のように、会社を休まなくてはいけない理由を具体的に伝えましょう。
可能であれば、休む当日ではなく、紛失した日に翌日の休暇を伝えるようにしましょう。日頃から貴重品の管理を徹底し、万が一に備えて必要な手続きや対処法を確認しておくことが大切です。
【例文】
昨日、財布を紛失してしまいました。警察への届け出とカードの再発行手続きを行うために、明日は一日お休みをいただきます。自宅の鍵も一緒に紛失しており、鍵の交換の立ち会いもする予定です。急な連絡で申し訳ありません。今後は、貴重品の管理に気をつけて、このようなことのないようにします。
交通事故などのトラブル
交通事故などのトラブルに遭った場合、警察への届け出や病院での診察、保険会社との手続きで、仕事を休まなければならないことがあります。
「通勤途中で事故に遭い、警察への届け出と診察が必要」「家族が事故に巻き込まれ、対応のため休む」など、具体的に伝えることで職場の理解が得やすくなります。
事故後は速やかに上司に連絡し、必要な手続きを確認することが重要です。急な事態にも冷静に対応できるよう、事前に連絡方法を整理しておくとよいでしょう。
【例文】
通勤途中で交通事故に遭い、警察への届け出と診察が必要なためお休みします。諸手続きも併せて対応してきます。急な連絡となり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
車が動かないなどのトラブル
車のバッテリー上がりや故障などのトラブルが発生したときにも、緊急の対応が必要になります。また、車で通勤をしている場合には、通勤手段が確保できずに出社が難しくなってしまいます。
そのような場合、「車が故障し、修理対応が必要で、出社できない」「エンジントラブルで動かせず、レッカー手配のため休む」など、具体的に伝えることで職場の理解を得やすくなります。
トラブルに備え、日頃から車の点検を行い、代替の通勤手段を確保しておくことが重要です。事前に備えておけば、繁忙期などの場合は半休等で済ませられるでしょう。
【例文】
車が故障し、修理対応が必要なためお休みをいただきます。エンジントラブルで動かせないため、レッカー手配をしています。急な連絡となり申し訳ありませんが、なにとぞご理解のほどよろしくお願いいたします。今後は車の点検を徹底し、万が一に備えるようにします。
仕事の前日に休みを伝えられる理由

前日のうちに、翌日仕事を休む理由について、例文と共にまとめています。前日、伝えておくと業務の引き継ぎもできます。休みの当日も、気がねなく過ごせます。
・前日から体調が思わしくない
・家族の看病や介護
・葬儀などへの参列
・身内が危篤状態
・トラブルに対応するため
上記について、一つずつ見ていきます。
前日から体調が思わしくない
前日から体調が優れない場合、無理に出社すると症状が悪化し、業務に支障をきたす可能性があります。できるだけ、早めに休みたいことを伝えるようにしましょう。
シフト勤務で、当日休みで体調が悪い場合などには、「発熱と吐き気が続いており、病院に行ってきたが、感染症だったので、明日も休みます」というように、具体的に伝えると職場の理解を得やすくなります。
勤務中に体調が悪くなった場合は、「頭痛と関節痛があるので、明日は休んで病院に行ってきます」というように、早く回復して仕事への影響を抑えたいという意図を伝えます。
急な休みでも影響を抑えるため、対応を依頼する事項や進行中の業務の状況を共有すると、安心して休みを取ることができます。
家族の看病や介護
家族の体調不良や介護の事情で、仕事を休まなければならないことがあります。可能であれば、前日までに職場へ連絡しておくと、業務やスケジュールを調整できます。
「親が高熱を出し、病院へ付き添う必要がある」「同居する家族の体調が悪化し、介護のために休む」と、状況を具体的に説明すると、上司や同僚の理解を得やすくなります。
さらに、普段から在宅勤務の活用や業務の引き継ぎ方法について相談しておけば、急な休みが必要になった際も、職場への影響を最小限に抑えられます。
葬儀などへの参列
親族や知人の葬儀に参列するためにお休みを取る場合も、可能な限り前日までに職場へ連絡するのが望ましいでしょう。業務への影響を最小限にできます。
連絡時には、「親族の葬儀に参列するため休む」「遠方での葬儀に向かうため出社が難しい」など、簡潔かつ具体的に上司や同僚に伝えます。
また、会社に忌引休暇の制度がある場合は、事前に確認し、必要に応じて上司や人事担当者へ相談します。
身内が危篤状態
身内が危篤状態になった場合、緊急の対応が求められます。できるだけ早く職場へ連絡し、休みを申し出ます。
「親が危篤状態で、病院に駆けつける必要がある」「家族の容体が急変し、付き添いのため休む」など、具体的に伝えると、職場も状況を把握しやすくなります。
また、状況が落ち着いた後は、上司や同僚に連絡して、業務への復帰時期について相談するとスムーズです。
トラブルに対応するため
予期せぬトラブルが発生した際にも、仕事を休まざるを得ないことがあります。やはり業務への影響を最小限に抑えるために、できるだけ前日までに職場へ休みの連絡を入れます。
連絡時には、「自宅の水漏れが発生し、修理業者の対応が必要」「交通事故の処理で警察や保険会社と連絡を取る必要がある」など、状況を具体的に伝えると、職場もトラブル対応の休暇への理解を示してくれます。
また、トラブルの内容によっては半休やリモート勤務の選択肢も考えられるため、上司と相談しながら、スケジュールを調整するとよいでしょう。
前日より前から伝えておける仕事を休む理由

事前に予定を立てられる用事で仕事を休む場合には、前日よりも前に職場に伝えておきます。前日よりも事前に伝えておくことのできる理由をまとめました。
・冠婚葬祭への参列
・公的手続きのため
・資格試験や免許更新
・旅行
・帰省や両親が来るなどの家族の理由
・子どもの学校行事
・工事や退去の立ち会い
・定期検診や健康診断
上記について、一つずつ見ていきます。
冠婚葬祭への参列
冠婚葬祭は事前に日程が決まっていることが多いので、早めに職場へ報告して、休みの調整を行うようにしましょう。
「親族の結婚式に出席する」「遠方の葬儀に参列するため前日から移動が必要」など、具体的に伝えると理解を得やすくなります。
業務にできるだけ影響が少ないように、同僚への引き継ぎや、取引先や社内のスケジュール調整も早めに進めておきます。
公的手続きのため
公的手続きは平日にしか対応できないことが多いので、仕事を休むケースがあります。そのような場合、計画的に事前に休みを申請しておくのは大切な点です。
「引っ越しに伴う住民票の変更」「パスポートの更新手続き」など、手続きの理由を具体的に伝えると職場の理解を得やすく、休暇の申請もスムーズです。
また、手続きにかかる時間を考慮し、半休や時差出勤が可能か上司と相談しておきます。事前の調整で、仕事への影響を抑えることができます。
資格試験や免許更新
資格試験や免許更新は、受験日や手続き可能な期間が決まっているため、早めに休みを申請し、業務に支障が出ないよう調整します。
「運転免許の更新手続き」「資格試験の受験」など、具体的に伝えることでスムーズに休みを取得しやすくなります。
また、試験勉強や必要な準備を計画的に進めることで、業務との両立がしやすくなります。余裕を持ったスケジュール管理を意識すると、楽な気持ちで休みの申請ができます。
旅行
旅行のために仕事を休む際は、事前に日程を調整し、業務に支障が出ないよう計画的に休暇を取得します。
例えば、「家族旅行のため○日から○日まで休む」「リフレッシュを兼ねて旅行を計画しているため、有休を取得する」と具体的に伝えると、スムーズに休みを取得しやすくなります。
繁忙期を避ける、早めに上司へ相談する、業務の引き継ぎをしっかり行うなど、準備を整えておくと安心して旅行を楽しめます。
帰省や両親が来るなどの家族の理由
帰省や親の訪問など家族に関わる理由で休む場合は、事前に日程を調整し、業務への影響を最小限に抑えることが大切です。
「実家に帰省し、家族と過ごすため休む」「両親が遠方から来るため、自宅で対応する必要がある」と具体的に伝えるようにします。
繁忙期を避ける、早めに休みを申請する、業務の引き継ぎをしておくなど、準備を整えておきます。そのようにすれば、家族と過ごすことは、仕事を休む理由として職場で受け入れられるものです。
子どもの学校行事
子どもの入学式や卒業式、授業参観などの学校行事は、事前に日程が決まっているので、早めに休みを申請しておきます。
「子どもの運動会に参加するため休む」「学校の面談があり、出席が必要なため休暇を取得する」と具体的に伝えると、スムーズに休みを取得しやすくなります。
事前に業務の引き継ぎを行い、同僚と調整しておきます。
工事や退去の立ち会い
自宅の工事や引っ越しに伴う退去の立ち会いは、指定された日時に対応が必要なため、早めに休みを申請しておきます。
「自宅の設備工事があり、業者の立ち会いが必要なため休む」「引っ越しの退去立ち会いのため、○日に休暇を取得する」と立ち会いの必要性を具体的に伝えると、状況を理解してもらいやすくなります。
スケジュールが決まり次第、上司に相談し、業務の調整や引き継ぎを早めに進めておくようにします。
定期検診や健康診断
定期検診や健康診断は、事前に受診できる期間が決まっています。日程を調整した上で早めに休みを申請し、スムーズに対応できるよう準備することが重要です。
「年に一度の健康診断を受診するため休む」「持病の定期検診があり、病院へ行く必要がある」と具体的に伝えるようにします。
午前休や半休を活用し、業務に支障が出ないよう調整すると、有給休暇などを効率的に取得することにもつながります。
仕事を休む際に意識しておきたいマナー

仕事を休む際に意識しておきたいマナーをまとめました。このマナーを覚えておくと、職場の周囲の人たちの印象も良く、休暇も取得しやすくなります。
・基本的には直属の上司に電話する
・同じ理由を繰り返さない
・無断欠勤をしない
・月曜日に休みを集中させない
・始業10分前には連絡を入れる
・うその「身内の不幸」を使わない
・用事がなければ外出しない
・SNSなどへの投稿をしない
・アポイントがあるときは自分で連絡を入れる
・出勤時には周囲にお礼を伝える
上記について、それぞれ見ていきます。
基本的には直属の上司に電話する
仕事を休む際は、基本的に直属の上司に電話で連絡し、理由と必要な対応を簡潔に伝えることが原則です。上司が席を外している際には、伝言を頼んで、連絡のつく時間を聞いておきます。そして、再度連絡するようにします。
「体調不良で休みます」だけでなく、「発熱があり医師の診察を受けるため、本日は休みます」と具体的に説明すると、信頼関係を保ちやすくなります。緊急時以外は、メールやチャットだけで済ませず、まずは電話で報告し、その後、必要に応じて文書で補足しましょう。
同じ理由を繰り返さない
同じ理由で何度も休むと、職場から不信感を持たれる可能性があります。休む理由は、適切に伝え、必要に応じて説明の仕方を工夫することが重要です。
「毎回体調不良を理由にする」「家族の事情を頻繁に持ち出す」と指摘されるような表現は避けましょう。できるだけ具体的な状況を伝えて信頼関係をこわさないようにします。
慢性的な体調不良や、家庭の事情が続く場合は、上司と相談し、業務負担の調整や在宅勤務の活用を検討します。
無断欠勤をしない
無断欠勤は職場の信頼を損なうだけでなく、業務にも支障をきたします。やむを得ない事情がある場合でも、必ず事前に連絡を入れることが重要です。
「体調不良で連絡できなかった」「寝坊して報告を忘れた」といった理由で無断欠勤をすると、多くの場合、上司や同僚に迷惑をかけることになります。
連絡が難しい状況には、家族や同僚に代わりに伝えてもらう、メールやメッセージを活用するなど、対応策を考えておくようにします。
月曜日に休みを集中させない
月曜日や休み明けの日に、繰り返し休むと、上司や同僚から「計画的に休んでいるのではないか」「休み疲れで仕事を休んでいるのでは」と疑われてしまう可能性があります。
「週明けの疲れが取れない」「気分が乗らない」といった理由は、仕事を休む正当な理由として受け入れられにくいものです。職場での信頼も損なうリスクがあります。
休暇明けに頻繁に休むのは避けて、日頃から体調管理を意識しましょう。やむを得ず月曜日に休む場合は、具体的な理由を明確に伝え、他の曜日とバランスを取りながら休みを調整するのが望ましいでしょう。
始業10分前には連絡を入れる
当日に仕事を休む際は、始業直前ではなく、少なくとも始業10分前までに連絡を入れ、職場が対応しやすいよう配慮するのが通常のマナーです。職場によって異なるルールやマナーもあるので、勤務先の原則を確認しておきましょう。
「体調不良で休む場合は早めに連絡し、業務の引き継ぎをスムーズにする」「突然のトラブルでも、可能な限り開始前に報告する」など、職場の混乱を防ぐ意識が求められます。チームでの業務が多い場合は、早めに連絡を入れて周囲の負担を減らすよう心がけます。
うその「身内の不幸」を使わない
「身内の不幸」を理由にうそをついて休むと、職場での信用を大きく損なうだけでなく、後に矛盾が生じた際に深刻な問題へ発展する可能性があります。
「〇〇さん、前にも親戚が亡くなったと言っていたのでは?」と不自然に思われると、信頼の回復は難しくなります。正当な理由がない場合は、「私用のため休みます」など、無理に詳細を説明せず、シンプルに伝える方が誠実な対応となります。
用事がなければ外出しない
体調不良を理由に休んだにもかかわらず外出しているところを同僚に見られると、不信感を持たれて、職場での信用を失う可能性があります。
体調不良で休んだ日に、やむを得ず外出する場合は、「病院へ行く」「必要な買い物を済ませる」など、正当な理由がある場合だけにしておきます。
繁華街など人目につく場所は誤解を招くため避け、基本的には自宅で静養しましょう。
SNSなどへの投稿をしない
仕事を休んだ日にSNSへ投稿すると、「本当に休む必要があったのか?」と疑われ、職場での信頼に影響を与える可能性があります。
「体調不良」と伝えて休んだにもかかわらず、旅行や遊びに関する投稿をすると、不適切な行動とみなされることがあります。休んだ日はSNSの利用を控えるか、少なくとも職場の人に見られる可能性がある投稿は避けるのが無難です。
アポイントがあるときは自分で連絡を入れる
仕事を休んだ際に、取引先や関係者とのアポイントがある場合は、自分で連絡し、日程調整や代替対応を行うのが原則です。
「本日の打ち合わせを体調不良で延期したい」「担当変更が必要なため、代わりの者が対応する」といった連絡を入れて調整すると、信頼を維持することができます。
上司や同僚に任せず、自ら対応することは、良い印象につながります。
出勤時には周囲にお礼を伝える
仕事を休んだ後に出勤した際は、業務をフォローしてくれた上司や同僚にお礼を伝えるのが、職場の信頼関係づくりに必要なマナーです。
「昨日は急に休んでしまい、ご迷惑をおかけしました」「フォローしていただきありがとうございました」など、簡単な一言を伝えるだけでも印象が良くなります。
感謝の気持ちを示すことで、今後も休みを取りやすくなます。
理由もなく休みたいと思ったときの対処法

・信頼できる上司や同僚に相談する
・なぜ休みたいのか理由を考える
それぞれの方法について、解説していきます。
信頼できる上司や同僚に相談する
特に理由はないが仕事を休みたいと感じたときは、一人で抱え込まず、誰かに相談するようにします。一人で悩み続けていると、状況が悪化することもあります。
信頼できる上司や同僚、社内の相談窓口や人事担当者、専門機関など、話しやすい相手を見つけるとよいでしょう。
「最近疲れがたまっていて、休みを取りたい」「モチベーションが下がっている」など、率直に話してみます。「繁忙期でなければ、有給休暇を取ってみたら」といった、適切なアドバイスを得られることもあります。
相談することで、仕事の負担を調整してもらえる可能性があり、休むべきかどうかの判断もしやすくなります。
なぜ休みたいのか理由を考える
なぜ休みたいのか、漠然としている理由について考える方法を紹介します。
・職場への不満を書き出す
・解決策を考えてみる
それぞれについて、手順を説明します。
職場への不満を書き出す
仕事を何となく休みたいと感じるときは、まずは自分の気持ちを整理することが大切です。
職場での不満やストレスの原因を「業務量が多くて負担を感じる」「上司とうまく意思疎通ができない」など、できるだけ具体的に書き出してみると、自分が何に疲れているのかが見えてきます。
原因がはっきりすれば、対処法を考えやすくなり、ただ気が乗らないだけなのか、本当に休息が必要なのかを冷静に判断できるようになります。
解決策を考えてみる
仕事を休みたい理由を具体的に整理できたら、それぞれについて解決策を考えてみます。
業務量が多い場合は、上司に相談して調整できれば、改善を期待できます。人間関係にストレスを感じるときは、適度な距離を取ると気持ちが楽になることもあります。モチベーションが下がっている場合は、意識的にリフレッシュの時間を作って、前向きな気持ちを取り戻すようにします。
それでも解決せず、休みたい気持ちが続く場合は、有給休暇を計画的に取得するなど、働き方を見直してみましょう。
休む理由がなくても仕事を休んでもよい
仕事を休む明確な理由がない場合でも、心身のリフレッシュやストレス解消のために休みを取ることは、問題ではありません。「理由がないと休んではいけない」と思い込まず、有給休暇は労働者の権利であることを理解し、計画的に活用することが大切です。適度に休息を取ると、仕事の効率やモチベーションが上がり、長期的にも良い結果につながります。
有給休暇を利用したり一定期間休職したりする
「気分転換のために一日休む」「疲れがたまっているので休養を取る」など、疲労回復やリフレッシュのために有給休暇を計画的に活用することをおすすめします。
一方で、「心身の不調が続いている」「仕事への意欲が低下し、業務に支障が出ている」場合は、無理をせず休職を視野に入れてみます。
休職を考える際は、会社の就業規則を確認し、制度の利用条件を把握した上で、上司や人事担当者に相談しながら適切に手続きを進めましょう。
あまりにもつらければ転職も視野に入れる

仕事を休みたい気持ちが頻繁に続き、精神的にも肉体的にも限界を感じる場合は、転職を考えるのも一つの選択肢です。
「職場の環境が合わない」「業務量が多すぎて心身が疲弊している」など、根本的な問題が解決しない場合は、新しい環境を探すことが必要かもしれません。
転職を検討する際は、まず現職で改善できることがないか試し、その上で転職エージェントの活用やキャリアの見直しを行うとよいでしょう。
仕事に関するお悩みがあればジョバディにご相談ください
今回は、仕事を休む理由の伝え方と、これといった理由がなくても仕事を休みたいときについて解説しました。
仕事がつらくて休みたいと感じているなら、ジョバディに相談して転職を検討してみませんか?
ジョバディでは、あなたのスキルや希望に合った求人紹介はもちろん、キャリア相談、条件交渉、面接対策など幅広いサポートを提供しています。転職に不安がある方も、一人ひとりに寄り添ったサポートで、納得のいくキャリア選びをお手伝いします。
まずは無料登録から。あなたに合った働き方を、一緒に見つけましょう。