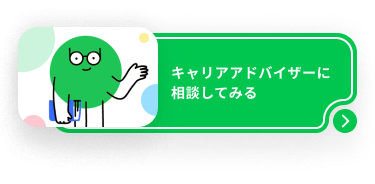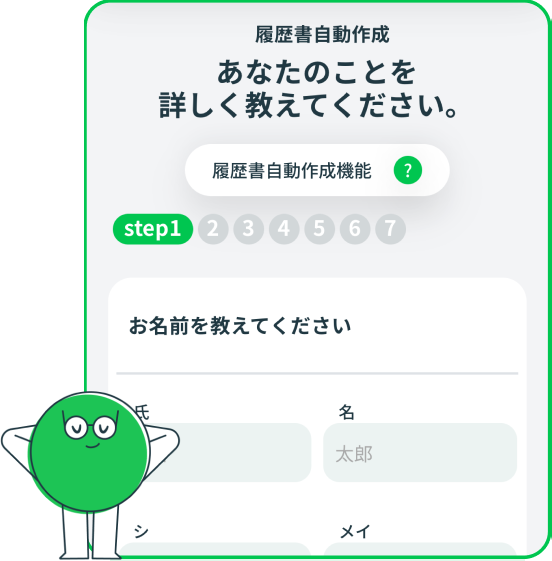退職の意向を上司にメールで伝えるには? 例文や送る際の注意点も解説
「退職しようと思っているけれど、退職の意向を上司に伝えるためには直接話をする方法しかないのか。メールで伝えることはできないのだろうか。また、退職の意向を伝える際にはどのような点に注意すればいいのだろうか」
この記事にたどり着いたあなたは、こんな疑問を抱えているのではないでしょうか。
上司に退職の意向を伝える方法に悩む人は多いですが、方法の一つとしてメールで伝えてよいのか迷うこともあります。退職の伝え方にはマナーがあり、適切な方法で伝えることでスムーズに話を進めやすくすることができます。
またメールで伝えると決めた場合、メールを送る際のポイントや例文を知っておくと、円満な退職につなげられます。
この記事では、退職の意向をメールで伝えようと考えている方へ、メールの例文や送る際の注意点などについて解説していきます。
この記事の要約としては以下の通りです。
●上司に退職の意向を伝える際は、基本的に口頭が望ましいが、在宅勤務や体調不良などやむを得ない場合はメールでも問題ない
●退職の意向を伝えるメールには、まず相談として送る方法と、正式な退職願として送る方法の2種類があり、状況に応じて使い分けることが重要
●退職の意向を伝える際には、希望日の1カ月前までに連絡し、就業規則を事前に確認することでスムーズな対応ができる
●メールの内容は簡潔かつ丁寧にし、「辞める」という直接的な表現は避け、敬意を持った言葉遣いを心がけることが望ましい
●退職後決定後のあいさつメールでは、上司・社内・社外向けに分けて送るのが一般的
それでは、解説を始めていきます。
上司に退職をメールで伝えるのは問題ない
退職の意向を上司にメールで伝えることは、特に問題ありません。
ここからは、法律やマナーの観点からメールで退職を伝えることが本当に問題ないのか、また、メールを送る際の方法について解説していきます。
具体的な内容は以下の通りです。
・口頭がマナーだがメールでも法律上問題はない
・メールでも2通りの方法がある
それでは一つずつ解説していきましょう。
口頭がマナーだがメールでも法律上問題はない
退職の意向を伝える方法には口頭とメールがあり、状況に応じて適切な手段を選ぶことが大切です。法律上はメールでの退職意思表示も有効とされており、必ずしも口頭で伝える必要はありません。
しかし職場の慣習や上司との関係性によっては、メールのみでは不十分と判断されることがあるため、慎重に判断することが重要です。メールのみでは不十分であると判断される可能性がある場合は、退職のことも含め、重要な決定を伝える際には口頭で伝えることが大切です。
例外として、病気やケガで出社できない場合や、何らかの事情で顔を合わせたくないなどの明確な理由がある場合には、メールで連絡しても問題はありません。
メールでも2通りの方法がある
退職の意向を伝えるメールには、上司への相談として送る方法と、正式な退職願として送る方法の2通りがあります。
相談として送る場合は、まず上司に面談の機会をお願いし、直接話す場を設けることが望ましいでしょう。
正式な退職願として送る場合は、退職日や理由を明記し、必要に応じて書面での提出も求められる可能性があります。
メールで退職の意向を伝える際には、上司の性格や職場の雰囲気に応じて、メールでの連絡は本当に問題がないのかどうかじっくり検討してから行うようにしましょう。
上司に退職を切り出す際のメールを送るマナー
円満に退職をするためには、退職を切り出すタイミングやマナーなど注意すべきことがいくつかあります。
ここからは上司に退職を切り出す際のメールを送るマナーについて解説していきます。
具体的な内容は以下の通りです。
・退職希望日の1カ月前にはメールをする
・直属の上司と話すアポイントを取る
・アポ取りのメールを送る
・本文中で「辞める」とは書かない
それでは一つずつ解説していきましょう。
退職希望日の1カ月前にはメールをする
退職の意向を伝えるメールは、退職希望日の1カ月前までに送るのが一般的なマナーとされています。法律上では、雇用期間の定めがない場合は2週間前までに退職を願い出れば問題ないとされていますが、余裕を持って遅くても1カ月前までには伝えるのが無難です。
しかし就業規則によっては、1カ月以上前の申告が必要な場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
急な退職は業務の引き継ぎに支障をきたす可能性があるため、できるだけ早めに意思を伝えるようにしましょう。
事前に就業規則を確認する
前述したように、退職の意向は一般的には退職希望日の1カ月前までに申告することが望ましいのですが、会社によっては2~3カ月前の申告が求められる場合もあります。
退職の申し出期限は企業ごとに異なるため、事前に就業規則を確認しておくことが重要です。
就業規則を確認せずに退職を申し出ると、社会人としてマナー違反となってしまう上、トラブルや引き継ぎの遅れにつながる可能性があるため注意が必要です。
勤務先の就業規則をしっかり確認し、その内容に従って申告しましょう。

直属の上司と話すアポイントを取る
就業規則を確認し退職希望日を決めたのち、退職の意向をメールで伝える際は、まず直属の上司と話すためのアポイントを取ることが重要です。
これは退職の内諾をもらうためではなく、退職希望日に合わせて実際の退職日を決定したり、引き継ぎのスケジュールを組んだりする必要があるためです。
メールには「退職についてご相談したいので、お時間をいただけますか」といった内容を簡潔に記載しましょう。
上司の都合を考慮し、できるだけ早めに面談の機会を設けることで、円滑に話を進めやすくなります。
在宅勤務の場合
在宅勤務の場合でも、まずはメールで上司に退職の相談を持ちかけ、オンライン面談の機会または直接対面する機会を確保しましょう。
完全リモートワークで勤務していたり、会社の所在地が遠くにあったりして直接会うことが難しい場合でも、メールだけで済ませず、丁寧なコミュニケーションを心がけることが重要です。
Web会議ツールや電話を活用し、できるだけ対面に近い形で退職の意向を伝えることがマナーとされます。
休職中の場合
休職中に退職を決意した場合でも、まずは上司にメールで意思を伝え、今後の対応について相談することが重要です。休職中の場合には、メールですべて完結させてもらえる可能性があります。
休職期間中の体調や自身の現状について説明し、復職が難しい旨や治療に専念したい旨をしっかり伝えましょう。
会社の規定によっては、復職手続きを経てから退職の手続きを進める必要があるため、事前に確認しておくことが大切です。
また、体調が優れない場合は、無理のない範囲で連絡を取り、必要に応じて家族や産業医を通じて相談することも選択肢となります。
上司が多忙な場合
上司が多忙な場合でも、退職の意向はできるだけ早めに伝え、面談の機会を調整することが重要です。上司が多忙で直接会う機会がなかったり、出張続きだったりした場合、退職の意向を伝えられず希望する退職日が先延ばしになってしまう可能性もあります。
そのため、まずは早めにメールで面談のアポを取るようにしましょう。
メールを送る際は、簡潔に用件を伝えつつ「お忙しいところ恐れ入りますが、ご相談の機会をいただけますか」と配慮を示すようにしましょう。
上司のスケジュールを考慮し、面談の候補日時を複数提示すれば、調整もスムーズになります。
アポ取りのメールを送る
退職の意向を伝える前に、まずは上司との面談のためのアポイントメールを送ることが重要です。
メールの内容は簡潔にし、「退職についてご相談したいので、お時間をいただけますか」と丁寧に依頼しましょう。基本的に面談の内容については直接伝えることが望ましいため、アポイントメールを送る際には、面談の機会が欲しいという要点のみを伝えるようにしましょう。
候補日時を複数提示し、上司の都合に配慮すると、面談の調整がしやすくなります。
アポを取る際の例文
ここでは、上司にアポを取る際の例文を紹介します。
メールの書き方をどうすればいいか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
例文
件名:面談のお願い 本文: 〇〇さま お疲れさまです。(氏名)〇〇です。 突然で申し訳ございませんが、折り入ってご相談したいことがございます。 つきましては、近いうちに会議室などの別室にて30分程度お時間をいただくことは可能でしょうか。 直近ですと、〇月〇日~〇月〇日の期間でお時間をいただければと考えております。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご検討のほどなにとぞよろしくお願い申し上げます。 (署名) |
前述もしましたが、アポを取る際には面談の内容は詳しく書かず、面談の機会が欲しい旨を簡潔に伝えるように心がけましょう。
上司の都合も配慮しつつ、自分の都合のつく日時をいくつか提示したメールを送っても問題はありません。
本文中で「辞める」とは書かない
退職の意向を伝える際は、メールの本文中で「辞める」という直接的な表現は避けましょう。強い言葉を使うと上司にネガティブな印象を与える可能性があるため、慎重な言い回しを心がけることが重要です。
「仕事を辞める」「この時期に退職したい」などの言葉を先に伝えてしまうと、退職を引き留められたり、面談の機会をなかなか作ってもらえなかったりと、スムーズに退職へ進めなくなる可能性もあります。
メールを送る際には「退職を考えております」「一度ご相談させていただけますか」など、柔らかい表現を用いることで円滑なコミュニケーションにつなげることができます。

【パターン別】上司に退職を伝えるメールの例文
上司に退職を伝えるメールを送る際には、上司に対して礼儀やマナーを心がけることが特に大切です。
ここからは、パターン別に上司に退職を伝えるメールの例文などを紹介します。
具体的なパターンは以下の通りです。
・事前に退職の意思を伝える場合
・退職願を送る場合
それでは一つずつ解説していきましょう。
事前に退職の意思を伝える場合
前述もしていますが、退職の意思を事前に伝える場合は、まず上司に相談する形でメールを送るようにします。
本文には「退職を考えており、一度ご相談させていただけますでしょうか」などと柔らかい表現を用いるようにしましょう。
具体的な退職日程は面談後に決めるため、この時点では詳細を確定させず、上司の意向を伺う姿勢を示すことが重要です。
例文
件名:退職面談のお願い 本文: 〇〇さま お疲れさまです。(氏名)〇〇です。 突然のご連絡申し訳ございません。 現在退職を考えており、一度ご相談させていただきたく、ご連絡いたしました。 つきましては、〇月〇日~〇月〇日の期間に、会議室などの別室にて30分ほどお時間をいただくことは可能でしょうか。 また詳細に関しましては、面談時にお話しできればと考えております。 お忙しいところ大変恐縮ではございますが、なにとぞご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 (署名) |
退職願を送る場合
退職願を送る場合は、上司に事前に相談した上で、正式な手続きとしてメールを送るのが望ましいでしょう。
件名は「退職願提出の件」とし、本文には退職希望日や理由を簡潔に記載しましょう。
会社の規定によっては、メール送付だけでなく、書面での提出が必要な場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
例文
件名:退職願提出の件 本文: 〇〇さま お疲れさまです。(氏名)〇〇です。 退職願を以下の通り送付させていただきます。 お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 退職願 令和〇年〇月〇日 〇〇株式会社 代表取締役社長 〇〇〇〇さま 〇〇部〇〇課 (氏名)〇〇〇〇 印 私議、 このたび一身上の都合により、勝手ながら来る令和〇年〇月〇日をもって退職させていただきたく、ここにお願い申し上げます。 以上 |
退職願の最低限のルール
退職願には、退職希望日・氏名・提出日を明記し、簡潔かつ正式な表現を用いることが重要です。
「一身上の都合により退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」とし、詳細な理由は記載しないのが一般的なマナーとなっています。
会社の規定によっては書面での提出が必要な場合があるため、メール送付前に確認しておくことが望ましいです。
なお退職願は退職したいと願い出るときの書類であり、正式に退職すると届け出るときには退職届を提出します。そのため文末が、退職願のときには「退職いたしたく、お願い申し上げます」となるのに対し、退職届では「退職いたします」と言い切る形になります。
円満退職を目指す場合には、退職願を選択することが一般的です。
退職のメールを上司に送る際の注意点
退職のメールを上司に送る際には、気持ち良く対応してもらうためにも上司への配慮が必要です。マナー違反と捉えられないようにするためにも、送る時期や内容などには気を付けましょう。
具体的な内容は以下の通りです。
・退職日ぎりぎりで送らない
・メールでしか連絡できない理由を書く
・退職の意思が固いことを伝える
・退職理由と退職希望日を明記する
それでは一つずつ解説していきましょう。
退職日ぎりぎりで送らない
退職の意向を伝えるメールは、退職日ぎりぎりではなく、最低でも1カ月前までに送るのが望ましいとされます。引き継ぎなどのことを考えると、1~2カ月程度は余裕を持って伝える方がよいでしょう。
しかし、会社の就業規則によっては、2~3カ月前の申告が必要な場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
退職日直前の連絡は、引き継ぎや業務調整に支障をきたす可能性があるため、余裕を持って伝えることがマナーです。
ちなみに期限が過ぎたからといって退職できないことはありませんが、円滑に退職手続きを済ませるためにも、周囲の状況を考える必要があります。
メールでしか連絡できない理由を書く
退職の意向をメールで伝える場合は、なぜメールで連絡するのか理由を明記することが重要です。
「在宅勤務が続いているため」「体調不良で出社が難しいため」など、具体的な事情を簡潔に伝えましょう。
理由を記載することで、上司に誤解を与えず、誠意を持って退職の意向を伝えやすくなります。
また理由とともにメールでの連絡となって申し訳ないという気持ちもアピールすることが大切です。
仮に上司が対面で相談すべきだという考えの人であっても、きちんとした理由があればわかってもらえるでしょう。
退職の意思が固いことを伝える
退職のメールでは、迷いがあるような表現を避け、退職の意思が固いことを明確に伝えることが重要です。退職を迷っているような内容だと、引き留めれば気持ちが変わるかもしれないと上司から強く説得される可能性があります。
「退職を考えている」といった表現よりも、「一身上の都合により退職を決意いたしました」といった確定的な表現を用いるようにしましょう。
ただし、強い言い回しではなく、礼儀をもって伝えることで、円満な退職につなげることができます。
退職理由と退職希望日を明記する
退職のメールには、退職理由と退職希望日を明記し、上司に意向が正しく伝わるようにすることが重要です。
ただ「退職します」だけでは上司も納得できないため、退職理由は「一身上の都合により」と簡潔にし、詳細な説明は求められた場合に伝えるのが一般的です。
退職希望日は具体的な日付を記載し、会社の規定や業務の引き継ぎを考慮して適切なタイミングを選ぶようにしましょう。会社に残る人になるべく迷惑がかからないように十分配慮して連絡することが大切です。

退職決定後のあいさつメールの書き方
退職決定後はこれまでお世話になった人たちへのあいさつも必要です。このあいさつもメールで行うことができます。多くの人へあいさつが必要な場合はメールを活用し、失礼のないように振る舞うことも大切なことです。
ここからは退職決定後のあいさつメールの書き方について解説していきます。
メールの送付先は以下のようになります。
・上司向け
・社内向け
・社外向け
それでは一つずつ解説していきましょう。
上司向け
退職が決まったら、これまでの感謝を伝えるために上司宛のあいさつメールを送ることが重要です。
本文には「お世話になりました」「ご指導いただき感謝しております」など、これまでの支援へのお礼を含めましょう。
退職日や今後の連絡先を記載し、最後まで誠意を持った対応を心がけることで、円満な退職につなげることができます。
例文
件名:退職のごあいさつ 本文: 〇〇部 部長 〇〇さま お疲れさまです。〇〇部〇〇課の〇〇です(氏名)。 このたび、一身上の都合により本日をもちまして退職する運びとなりました。 本来であれば直接お伺いするべきところ、メールでのごあいさつとなり申し訳ございません。 〇〇部長には入社時より多くのことを学ばせていただき、大変お世話になりました。在職中は至らぬ点も多かったと思いますが、丁寧にご指導いただき心から感謝しております。 今後も教えていただいたことを糧に、さらに成長できるように励んでまいりたいと存じます。 退職後、何かございましたら以下の連絡先にご連絡をいただけますと幸いです。 電話番号: メールアドレス: 最後になりましたが、〇〇部長のさらなるご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。 (署名) |
社内向け
退職が決まったら、社内向けにもあいさつメールを送り、これまでの感謝を伝えることが重要です。
本文には「在職中は大変お世話になりました」「皆さまとご一緒できたことをうれしく思います」などの感謝の言葉を含めるようにしましょう。
また、退職日や引き継ぎ担当者の情報を明記し、必要に応じて個人の連絡先を記載することで、円滑な関係を維持しやすくなります。
例文
件名:退職のごあいさつ 〇〇部〇〇課 〇〇(氏名) 本文: 〇〇課の皆さま、お疲れさまです。〇〇(氏名)です。 私事で恐縮ではございますが、このたび、一身上の都合により、会社を退職することとなり、本日が最終出社日となりました。 本来であれば皆さまへ直接ごあいさつに伺うべきところですが、メールにて失礼いたします。 入社後から〇〇課の皆さまには、大変お世話になりました。 業務を通して多くのことを学び、経験を積ませていただきました。 皆さまとご一緒できたことをうれしく思うとともに、心より感謝を申し上げます。 この会社で学んだことを生かして、今後も励んでまいりたいと思います。 なお、今後の連絡先は下記となります。何かございましたら、ご連絡をいただけますと幸いです。 メールアドレス: 電話番号: 最後になりましたが、皆さまのさらなるご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。 今まで本当にありがとうございました。 (署名) |
社外向け
取引先や関係者など社外向けのあいさつメールでは、退職の報告とこれまでの感謝を簡潔に伝えることが重要です。
本文には「これまでご指導いただき誠にありがとうございました」「在職中のご厚情に深く感謝申し上げます」などの丁寧な表現を用いるようにしましょう。
後任者の連絡先を記載し、今後の業務に支障が出ないよう配慮することで、円満な関係を維持することができます。
例文
件名:退職のごあいさつ【株式会社〇〇〇 氏名〇〇 〇〇】 本文: 株式会社△△△ △△部 △△さま いつもお世話になっております。株式会社〇〇〇の〇〇(氏名)です。 私事で大変恐縮ではございますが、このたび、〇月〇日をもって株式会社〇〇〇を退社する運びとなりました。最終出社日は、〇月〇日の予定です。 △△さまには、これまで何かとご指導いただき誠にありがとうございました。 在職中のご厚情に深く感謝申し上げます。 後任は同じ部署の□□が担当いたします。 退職までにしっかりと業務を引き継いでいきますので、どうぞご安心ください。 つきましては、〇日にお伺いする際に後任の□□と一緒にごあいさつさせていただければと存じます。 どうぞよろしくお願いいたします。 (署名) |
退職まで訪問予定がない場合は後任の紹介も
退職までに取引先や関係者を訪問する機会がない場合は、メール内で退職のあいさつと後任者を紹介することが重要です。
本文には直接あいさつできないことへのおわびと、「後任の□□が引き続き対応させていただきますので、よろしくお願いいたします」と後任者の紹介について記載しましょう。
後任者の氏名・連絡先を明記し、スムーズな引き継ぎを強調すると取引先との信頼関係を維持しやすくなります。
取引先や関係者に、退職後の不安を感じさせないような文面を意識することが大切です。

退職のあいさつメールを送る際のポイント
前述してきましたが、退職のあいさつメールを送る際には、相手への配慮やこれまでお世話になった感謝の気持ちを伝えることが重要です。
またそのほかにもいくつか気を付けるべきポイントがあります。
そこでここからは退職のあいさつメールを送る際のポイントについて解説していきます。
具体的な内容は以下の通りです。
・シンプルな内容で問題ない
・Bccでの一斉送信で問題ない
・退職理由は「一身上の都合」にする
・社内向けは最終出勤日に送る
・社外向けは最終出勤日の2~3日前に送る
・転職先が決まっても企業名は伏せる
それでは一つずつ解説していきましょう。
シンプルな内容で問題ない
退職のあいさつメールはシンプルな内容で問題なく、感謝の気持ちを伝えることが最も重要です。
長文になりすぎず、「これまでお世話になりました」「心より感謝申し上げます」など簡潔にまとめましょう。
詳細な経緯は不要なため、読みやすさを意識し、必要最低限の情報をわかりやすく伝えることが大切です。
社員数が多かったり、周囲と関わる機会が少ない業務に就いていたりした場合、全員と面識があるとはいえない部分もあるかもしれません。このような場合のためにも退職のあいさつは、退職する旨と感謝の気持ちが伝わるような文面であれば、シンプルな内容で問題ありません。
Bccでの一斉送信で問題ない
退職のあいさつメールは、Bccで一斉送信しても問題なく、効率的に感謝の気持ちを伝えることができます。
ToやCcを使用すると、受信者同士のアドレスが表示されてしまうため、プライバシーに配慮することが重要です。
個別に連絡を取りたい相手がいる場合は、別途個別メールを送ることで、より丁寧な印象を与えることができます。特に、業務上関わる機会が多く、お世話になった上司や同僚には、個別であいさつメールを送ることをおすすめします。
仕事での印象深かった経験や一緒に仕事していた際のエピソードなどを付け加えると、感謝の気持ちがより深く伝わるでしょう。
退職理由は「一身上の都合」にする
退職のあいさつメールでは、退職理由は「一身上の都合により」と簡潔に記載するのが一般的です。
具体的な理由を詳しく書く必要はなく、簡潔にすることで受け取る側に余計な詮索をさせない配慮となります。
ポジティブな印象を残すため、「今後の新たな挑戦に向けて」「これまでのご支援に感謝しております」と前向きな言葉を添えるとよいでしょう。
社内向け・社外向けのどちらにしても、「一身上の都合」と記載するのが無難です。
社内向けは最終出勤日に送る
社内向けの退職あいさつメールは、最終出勤日に送るのが一般的なマナーです。
早すぎると業務に影響を与える可能性があり、遅すぎると十分なあいさつができないため、適切なタイミングを選ぶことが重要です。ただし、企業の規則や退職時のガイドラインに決まりがあるようであれば、それに従うようにしましょう。
当日忙しくなることも考え、事前にメールを作成し、送信予約を設定しておくとスムーズに対応できます。最終日に慌てなくて済むように、余裕を持って準備しておくことが大切です。
社外向けは最終出勤日の2~3週間に送る
社外向けの退職あいさつメールは、最終出勤日の2~3週間前に送るのが適切です。
直前すぎると引き継ぎの連絡が十分にできない可能性があるため、余裕を持って送信するようにします。
後任者の連絡先を明記し、業務が円滑に引き継がれるよう配慮することが重要です。
先方に引き継ぎ後の不安を与えないようにするためにも、事前に退職を知らせるメールを送り、可能であれば引き継ぎの後任者と一緒にあいさつに行くなど、早めの行動を心がけましょう。
転職先が決まっても企業名は伏せる
退職のあいさつメールでは、転職先が決まっていても企業名は伏せるのが一般的なマナーです。
「今後は新たな環境で挑戦する予定です」といった表現にとどめ、詳細を記載しないようにしましょう。
取引先や同業他社への転職の場合、トラブルを避けるためにも具体的な情報は控えることが望ましいです。
しつこく聞きだそうとしてくる相手には、業種や職種だけ答えたり、「後日改めてご連絡します」などとかわしたりした方がいいでしょう。

退職・転職の悩みがあるならジョバディに相談!
ここまで退職の意向をメールで上司に伝える方法について解説してきましたが、メールの送り方や送る際の注意点など、悩んでいたことを解消することはできたでしょうか。
今退職や転職で悩んでいる方や、面接対策に悩みがある人はぜひジョバディにご相談ください!
転職したくても退職のことが気になっているという人は、経験豊富なキャリアアドバイザーから円満退職のアドバイスをもらうことができます。
また、ジョバディでは3万件以上の豊富な求人情報から、あなたのスキルや希望に合った求人紹介はもちろん、キャリア相談や条件交渉、面接対策など多岐にわたるサポートを提供いたします。
サポートには、「せわやきサポート」「ほどよくサポート」「ひかえめサポート」の選べる3つのサポートタイプがあり、あなたのニーズに合わせてカスタマイズすることができます。
会員登録は無料で30秒あればできます。退職や転職についての悩みを早期解決するためにも、早速登録してみましょう!