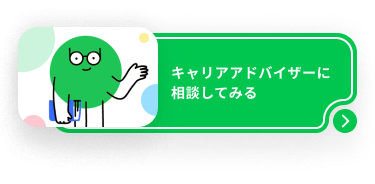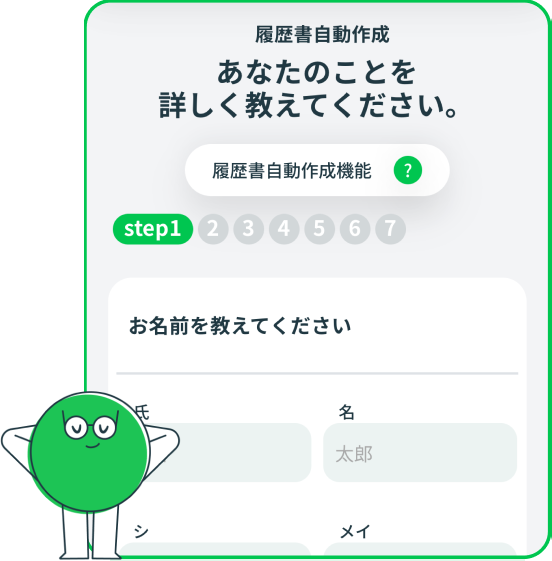既卒者の就活は厳しい? 重要視されるポイントや成功のコツを紹介
既卒者とは、すでに大学を卒業したものの、就職した経験のない人を指します。
本記事では既卒者の就活について、以下のようにまとめていきます。
●既卒者でも就活を成功させることは可能
●ただし、ネガティブなイメージがある、応募可能な企業が減る、即戦力と評価されにくい、空白期間がネックになるなどにより難易度は高い
●重要視されるポイントは、今までの失敗から何を学んだか、就活に向けて努力しているか、企業が求める人物像とマッチしているか
●成功させるコツは、自己分析と自己理解、自分から行動する、第三者の意見などにより視野を広げる、目標と期限を設ける、資格やスキルを取得しておく
これから就活を始める既卒者の方は気になったポイントや必要な知識を読んでみてください。
既卒の就活は難しい?
新卒入社のため、就職活動は大学在学中に行い内定を獲得するのが理想とされている現在では既卒でも就活を成功させられるのか不安になると思います。
まずは既卒の転職市場における立ち位置を確認し、知識を広げていきましょう。
既卒の定義
前述したように、既卒とは大学卒業後一度も就業経験のない方を意味します。一般的には卒業してから1~3年の人を指していることが多いようです。
同じように採用市場で使われている特定の層の呼び方と比較して違いを見ていきましょう。
・新卒
大学や専門学校、高校を卒業後はそのまま就職する人たちを指します。在学中に新卒枠への就職活動を行っているのが新卒として分類されるのに対して、既卒は卒業後に就職活動を始めている方やまだ就職できていない方を指します。
・第二新卒
よく既卒と混同される言葉に第二新卒があります。第二新卒は卒業してから1~3年程度の就業経験がある方を指します。第二新卒の就職は転職か再就職で、就業経験の有無が明確に違います。
・フリーター
フリーターとは一般的に卒業後、アルバイトやパートにより生計を立てている方を指します。就職をせずに卒業後フリーターとして過ごしていれば既卒でもありフリーターでもある、といったようにフリーターと既卒は明確な差はありません。
ただ、一度就職をした後に仕事を辞めて、アルバイトやパートのみで生活していればフリーターではありますが就業経験があるため既卒とはなりません。
上記のように、既卒という言葉は卒業後に就職した経験がなく、卒業後1~3年の人のことです。
既卒でも就活を成功させることは可能
結論を言いますと、既卒であっても就職活動を成功させることはできます。厚生労働省の「労働経済動向調査(令和5年8月)の概況」によると、令和4年度新規学卒者の採用枠で正社員の募集を行った事業所のうち「既卒者は応募可能だった」とする事業所の割合は計70%と高くなっています。また、そのうち38%は「採用にいたった」となっており、全体で見ると約4社のうち1社が既卒者を新卒採用枠での正社員として雇用していることになります。
中でも新卒採用枠での正社員募集に「既卒者は応募可能だった」とする割合の高い業界は「医療・福祉」で85%、次いで「宿泊業・飲食サービス業」が82%となっており、そのうち「採用にいたった」は前者が46%、後者が49%と非常に高くなっています。共通して若い働き手の不足が問題となっている業界です。
既卒の就活は実際にはそれほど厳しくなく、むしろ若い働き手の不足している企業は新卒だけでは人員を確保できずに既卒を積極的に採用しています。既卒としての応募枠だけではなく、新卒枠と合わせて応募をかけている企業を探し、しっかりと対策を講じることで既卒の就活は十分に成功し得ます。
既卒就活の難易度が高い理由
既卒就活には以下のような観点から、難易度が高いといわれています。
・就職しなかったことに対するネガティブなイメージがあるから
・応募可能な企業が減る
・即戦力があると評価されにくい
・空白期間がネックになる
既卒が就活で希望する企業や正社員として入社することは可能な一方で、難易度が高いことも事実です。難易度が高くなる理由を知って、正しく対策する必要性を理解しましょう。
就職しなかったことに対するネガティブなイメージがあるから
既卒者には、新卒で就活しなかったことに対してネガティブなイメージがどうしても付きまとってしまいます。「新卒としての就活が何かうまくいかなかった理由があるのではないか」「既卒になったのは怠慢だ」といったように考える方も少なくないようです。一方で卒業して間もないうちは新卒と同様に扱ってもらえる企業もあるため、イメージを払拭できるような対策を取りつつそのような企業を探してみてください。
応募可能な企業が減る
前述した内容から見ても、既卒者を含めない新卒限定の求人を用意している企業は30%ほど存在しています。これは日本に新卒一括採用の仕組みがあることや、新卒ではなく既卒やフリーターへのマイナスなイメージが存在していることが原因です。
特に「不動産業・物品賃貸業」の新規学卒者の採用枠で正社員を募集した際の既卒者の応募の可否及び採用状況について「応募不可だった」としている割合は43%、製造業であれば38%と、既卒者の応募できる企業が新卒者に比べて少なくなっている業界のあることがうかがえます。
即戦力を採用条件としている企業には評価されにくい
既卒者を中途枠で採用する企業もあります。しかし、そういった場合には即戦力となる経験者やスキル保持者を積極的に受け入れるような企業が多く、対して社会人経験のない既卒者は評価してもらいにくいため不利になってしまいます。また、業界によっては中途枠の応募条件である資格や経験について満たせない場合もあるなど書類選考すら通過するのが難しくなります。
結果として、既卒者は新卒学生に比べて職業選択の幅が狭まってしまうというデメリットがあります。
空白期間がネックになる
既卒者の就活では、就職活動を在学中に行っていなかったことや卒業後の「空白期間」を懸念することになります。卒業後にすぐ働いていなかった事実を「働く意欲が少ない」「採用しても長続きしない」と企業の採用担当者に思われてしまうかもしれません。
空白期間に何かしら理由があるとしても、その理由が履歴書に記載できない場合には面接まで企業側には伝わらないということも不利に働いてしまいます。
なぜ空白期間があったのか、どのようなことを空白期間に取り組んでいたかをしっかりと説明できるようにしておきましょう。
既卒の就活で重要視されるポイント
既卒者の就職活動において企業の人事が重視するポイントは以下の3点です。
・今までの失敗から何を学んだか
・就活に向けて努力しているか
・企業が求める人物像とマッチしているか
それぞれの細かい内容を確認し、対策を講じておきましょう。
今までの失敗から何を学んだか
既卒者に新卒で就職できなかった理由や学生時代に挫折した経験がある場合、就活ではそこから何を学んだかが重要視されています。失敗を真っすぐに受け入れて同じミスを繰り返さないための行動ができている場合は、その点を評価してもらえます。反対に、人や企業に失敗の原因を押し付けたままでは反省の色がないことや自分を振り返ることができない人間として見なされてしまいます。
既卒になってしまったことを悲観し続けたり隠し通そうとしたりするのではなく、「既卒になったことを踏まえてどう努力してきたか」をアピールしましょう。
就活に向けて努力しているか
既卒者の就活市場では、既卒者が前向きかつ主体的に就活を行い、努力しているかを見られています。「志望業界や企業について、実際のサービスや商品を利用する」「既卒採用や応募を取り扱っているか企業に問い合わせる」などのように、企業の求人や企業努力の情報収集などを積極的に行っていく姿勢を見せることで、就職に対して熱意がある誠実な人間としてアピールできます。
企業が求める人物像とマッチしているか
新卒採用や中途採用など採用の形に関わらず、企業は既卒者と自社の相性や適性を重要視しています。特に、企業の求人サイトに出してある人物像はその企業が今求めている人材です。その社風や求められる人物像に自身がマッチしていれば、今はスキルや経験がなくても、将来成長する見込みがあれば評価してもらえるでしょう。
一方で企業と自身との間に結び付きがなければ、優秀な人材であっても企業側が自社に合わないと判断し、選考が通らない場合があることに注意が必要です。
既卒が就活を成功させるコツ

既卒者が就活を成功させるためには、以下のようなコツを押さえておくとよいでしょう。
・自己分析を深める
・既卒になった理由を説明できるようにする
・自分から行動する
・第三者の意見を参考にする
・「既卒ならでは」の強みを理解しておく
・目標と期限を設ける
・資格やスキルを取得しておく
・視野を広げる
数が多いものの、一つ一つ大事な要素です。内容をしっかり確認し、企業が求めている人材や主体的な行動の重要さなど、理解を深めていきましょう。
自己分析を深める
既卒者の就職活動においてはまず改めて自己分析を行うのが得策です。というのも、新卒の就活時と、既卒経験を経て価値観が大きく変わっている部分は少なからずあると思われるためです。どこがどのように変化したのか、具体的に言語化しておきましょう。
自己分析では自分が仕事に求めていることや、自分が持つ強み・弱みなどを整理できます。また応募企業を選ぶ基準である就活の軸が明確になり、入社後のミスマッチが防ぎやすくなるなど、自己分析は就活を進める上で重要なポイントとなっています。丁寧に行いましょう。
自身に合った職種がわからない場合には適職診断などを受けるのもおすすめです。
既卒になった理由を説明できるようにする
前述したように、既卒者での就活において大切なのは「既卒者になったこと」ではなく「既卒者になったことを踏まえてどう努力してきたか」です。既卒者になって空白期間ができたこと自体が失敗である場合には、なぜそのような失敗をしたのか原因を見つめ直して、その反省と今後の行動を言語化しましょう。
既卒者となった理由は、企業の採用担当が最も気になるポイントです。必ず聞かれる質問のため、その理由と反省をしっかりとまとめて面接官を納得させましょう。
自分から行動する
前述したように「志望業界や企業について実際のサービスや商品を利用してよく調べる」「既卒者でも募集しているかを企業に問い合わせてみる」「面接もしくは面談の機会を得たら、とにかく採用担当者に会ってみる」など、既卒者の就活では主体的に行動することが大切です。
企業の求人や企業努力の情報収集などを積極的に行っている姿勢を見せて、熱意があることをアピールしましょう。
主体的に動くのが難しい方や、実際にどう動いたりサービスを分析したりしたらいいのかわからない方には転職エージェントを利用してアドバイスを受けるのがおすすめです。
第三者の意見を参考にする
既卒での就活を成功させる上では、第三者からの客観的なアドバイスを取り入れ、自己分析や志望企業選びに役立てるなど周囲の意見を参考にすることも重要です。周りの新卒採用された友人や先輩に相談しながら就職活動を進めると、モチベーションの維持や向上につながります。また、実際の仕事内容を知る機会にもなります。
「既卒ならでは」の強みを理解しておく
新卒には新卒の強みがあるように、既卒者には既卒の強みがあることを知っておくと、就職活動により取り組みやすくなります。
既卒者の強みとしては、以下のようなポイントが挙げられます。
・ほかの企業の社風に染まっておらず、若い人材としての柔軟性や将来性がある
・(フリーターをしていた場合に限り)特定のスキルがある
・新卒で就職活動をうまく終えられなかった挫折経験と、そこからの努力
・企業の希望する入社時期に合わせられやすい
これらの強みと供に、就活中に得た学びや卒業後の経験などを言語化して整理できるとアピールしやすいでしょう。
目標と期限を設ける
既卒者には就職活動をする時間が十分にある半面、就活が長引いてしまったりけだるく感じてしまったりすることがあります。そのようにならないよう、就活における期限や目標を明確に定めておくことをおすすめします。例えば今週中に1社エントリーする、1年で就活を終わらせるなど具体的にスケジュールを立てて行動すれば、モチベーションを維持しやすいでしょう。
資格やスキルを取得しておく
既卒者の就活に特別な資格やスキルは必須ではありません。しかし、意欲を伝えるために志望業界や職種で将来必要となるようなスキルや資格を取得してみるのも一つの有効な手段です。以下はおすすめの資格例です。
・ITパスポート
・簿記検定(2級以上が望ましい)
・介護職員初任者研修
関連する資格を有していることや現在勉強中であることは、その業界や企業への意欲をアピールしやすくなり、さらに業務や業種に関する知識も得られます。一方で資格取得には相応の難易度があるため、資格を取るためにあまり時間をかけすぎないよう、無理のない範囲で行うことが大切です。
視野を広げる
就職活動では「自分がやりたいこと」だけに絞らず「今の自分ができること」も踏まえて、幅広い業種や職種に興味を持つようにすることが大切です。そこから発展して、自分が将来どのようなスキルや経験を生かして仕事をしていたいのか具体的な目標を立てられるとより効果的な就活ができるようになります。
いきなり「将来の夢や希望」を考えることが難しい場合は、まずは社会人経験を積むことを目標に就職してから、改めてキャリアチェンジを検討するのも一つの手です。
また、就職活動で周囲の目を気にしたり自身のプライドで意固地になったりして大手企業だけにこだわることなく、いろいろな企業に興味を持つことで社会への知見が広がります。
既卒者におすすめの就活方法

既卒者を積極的に受け入れている企業は多くありますが、一方で求人を見付けることが難しい場合もあります。
以下の方法は既卒者が就活で求人を探す上で参考になります。
・転職エージェント
・求人サイト
・企業ホームページからの直接応募
・ハローワーク
・友人や知人の紹介
それぞれの活用方法を見ていきましょう。
転職エージェント
既卒者の就活で最もおすすめなのが、就活・転職エージェントの活用です。転職エージェントや就活サービスはたくさんありますが、その中でも20代や既卒者向けのサービスに登録すると就職活動をより進めやすくなります。
転職エージェントを活用するメリットとして、専任のキャリアアドバイザーが企業選びから就職時の条件交渉までサポートしてもらえる点があります。細かなヒアリングによってあなた自身に適した企業選びや求人探しをしてくれるため、既卒者の就活でネックとなっている「採用を行っている企業を探すのが難しい」という問題を解消できるのはもちろんのこと、入社後のギャップによる離職を防ぎやすくなるというメリットもあります。
また、書類作成や面接対策なども行ってもらえるため、選考対策に自信がない既卒者の方にもうってつけです。
サービスによって求人の得意分野が異なるため、自身に合った転職エージェントを利用することでより効果的に就職活動を進められます。
複数掛け持ちで登録できる点も考慮してみてください。
求人サイト
新卒での就職活動と同様に、求人サイトに登録して求人を探す方法もあります。
この求人サイトから始める就活は自分のペースで進められるのが魅力です。
一方で求人探しや応募先とのやりとり、応募書類の添削や面接練習を自身で行う必要があるため、多くの労力が必要となっています。
ほかにも求人サイトによって業界特化型であったりハイクラス専用であったり、とさまざまな種類の求人サイトがあります。若年層向けの既卒者に適した求人サイトに登録できるよう、「既卒者募集」「未経験可能」といったキーワードを記載している求人をもとに探してみてください。
企業ホームページからの直接応募
既卒者の就職活動として、興味のある企業のWebサイトや採用情報から応募する方法があります。この方法は採用担当に入社意欲が高い印象を持ってもらえます。ただし、一方で新卒採用や中途採用を行っている企業では既卒はそもそも募集を行っていなかったり、そもそも既卒向けの採用情報が未掲載だったりすることがあります。そういった場合には企業の問い合わせフォームなどからコンタクトを取れないか試してみましょう。
また求人情報を事前に把握することが難しいことも留意しながら連絡を取ってください。
ハローワーク
新卒や卒業後3年以内の既卒が利用できる「新卒応援ハローワーク」という若者向けの就職支援サービスがあります。この新卒応援ハローワークには地元の主に中小企業の求人掲載が多く、求人数自体も多いという特徴があります。
職業訓練の案内や地域の求人情報の紹介といったサービスを行っており、公共サービスのため、誰でも無料で利用できます。
ただし相談員はインセンティブがないため、転職エージェントほどに細かいサービスを受けられるわけではない点も考慮しておきましょう。
友人や知人の紹介
大学の友人や地元の先輩など、信頼している人からの紹介先で就職する方法もあります。社風や環境、労働時間などの企業内部の実態を把握した上で検討できるためミスマッチを防ぎやすい方法です。
ただ、選考通過後にほかの企業でやりたいことが見つかった場合などには選考辞退や退職しづらい点がネックとなるため、情報をくまなくリサーチして自己分析と合わせて自分に合った企業かどうか、丁寧に考えましょう。
既卒の就活で行いたい選考対策
・就職のために行った努力をアピールする
・自己PRと志望動機を結び付ける
・その企業だからこその志望動機を作る
・意欲の高さをアピールする
・よく聞かれる質問への回答を用意しておく
【既卒就活の質問例】1. どうして就職しなかったのですか
【既卒就活の質問例】2. 卒業してから何をしていましたか
【既卒就活の質問例】3. 就職しようと思った理由を教えてください
【既卒就活の質問例】4. 何か質問はありますか
上記は既卒就活において重要な選考対策です。
就職活動としてそもそも必要なポイントから、既卒としての就活対策まで押さえてあります。
しっかりと目を通して、選考通過を目指しましょう。
就職のために行った努力をアピールする
先ほども述べた通り、大切なのは「既卒になってしまったこと」ではなく「既卒になった事実を自分自身がどう受け止めているか」と、そこから「就職するためにどんな努力をしてきたか」をきちんと説明できるかになります。採用担当者は既卒になった理由を聞きますが、それは単に理由を知りたいのではなく、そこから何を学び、どう考え、どんな行動や努力をしているのかを知りたいために質問しているのです。
例えば「必要な資格を取得した」や「就職活動で企業の情報収集を積極的に行っている」といった前向きなアピールをすることが重要です。
自己PRと志望動機を結び付ける
既卒者に限らず、就職活動では単に志望動機を伝えるのではなく「自己PR」を交えながら述べるのがポイントです。応募企業に入社したら「これまでの自分のどういう経験を生かせるか」や、「自分の目標をこの会社ならどのようにかなえられるか」など、自分と企業の結び付きを具体的に説明することで、採用担当者に自分の特性やスキルが企業にマッチしていることをアピールできます。
企業との接点を知ることで、採用担当側としても採用希望者の実際に働いている姿を想像しやすくなり、志望動機の説得力が増すことにつながります。
その企業だからこその志望動機を作る
既卒者が面接で志望動機を話すとき、その企業でなければいけないと熱意が伝わるような内容を求められます。どの企業でも通用するような志望動機ではなく、その企業でなければならない志望動機を作成することが大切です。
前述した通り、その志望企業と自分とのマッチ度を十分にアピールするのが志望動機を伝えるコツです。自身のスキルや将来の展望と社風とのマッチする点を話し、企業の採用担当者に自分が働いている姿をイメージしてもらえるように志望動機をまとめておきましょう。
意欲の高さをアピールする

既卒者の就活において何かしらの実績や経歴がない場合は、その代わりに意欲をアピールすることになります。特に中途採用枠に応募した際には、ほかの中途採用希望者に比べて社会人経験やスキルの不足は否めません。
また、「平成30年若年者雇用実態調査の概況」によると、若年正社員の採用選考をした事業所のうち、採用選考にあたり重視した点は「新規学卒者」の採用、「中途採用者」の採用ともに「職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」を重視した事務所の割合が最も高く、それぞれ77.9%、76.0%となっています。その次に「コミュニケーション能力」が71.1%と62.9%、「マナー・社会常識」が61.0%と60.1%という結果となっています。以上のことからも、企業はスキル・経験よりも積極性や他者と円滑に仕事できる能力を重要視していることがわかります。
既卒者は就職活動で意欲やコミュニケーション能力をアピールできると採用につながりやすいでしょう。
よく聞かれる質問への回答を用意しておく
既卒者の面接でよく聞かれることとして、「空白期間は何をしていたのか」「既卒となった原因は何か」などが挙げられます。本番時に答えを考えるのではなく、あらかじめ質問を把握し、あらかじめ回答を用意しておけば落ち着いて対応できるでしょう。
以下に、既卒者の面接でよく聞かれる質問の回答例を紹介します。
【既卒就活の質問例】1. どうして就職しなかったのですか
多くの企業で聞かれる質問として、「なぜ新卒採用で就職しなかったのか」「できなかったのか」が挙げられます。これは企業の採用担当が既卒者に仕事への意欲が低いのではないかといった不安要素を感じているためです。
よって、就職しなかった理由を明らかにし、その後の行動で改善しようとしていると納得してもらえれば、採用担当者の不安を払拭できます。
回答例:就活をしていたが、内定を得られなかった。
「在学時にも新卒としての就職活動を行っておりました。しかし企業選び軸が明確ではなく、結果としてどの企業でもあいまいな志望動機のまま受けてしまい、内定を出していただけませんでした。原因は自己分析の不足による、価値観や自身の強みの理解が不十分だったと反省しております。その後、ほかの友人からのアドバイスや就職支援サービスを活用して自己分析を徹底的に行ったことで、やりたいことが見えてきたため就職活動を再開し、御社を志望しました」
【既卒就活の質問例】2. 卒業してから何をしていましたか
卒業して既卒者になってからの時間をどのように過ごしていたのかを聞かれるため、有効活用していたことを伝えます。空白期間を無駄にせず成長できたことをアピールできれば面接官の不安を払拭できます。
回答例:資格を取得しようとしている。
「卒業してから現在まではITパスポートの資格取得に向けて励んでいました。新卒採用のために就職活動をしていたときの経験を経て、IT分野で働くことに興味を持ち、そこから勉強を続けています。まだ取得できていませんが、実際に今IT系の仕事をしている友人からの助言を得て、単発の仕事などもいくつか受けています」
【既卒就活の質問例】3. 就職しようと思った理由を教えてください
応募してくれている既卒者が長期的に働いてくれるモチベーションの高い人材であるかを確認するための質問です。この質問には前向きな理由を具体的なエピソード付きで伝えることができれば、応募者の長期的に働く姿を採用担当に想像してもらえるため、志望動機の説得力が高まることが期待できます。
回答例:同級生の友人から刺激を受けた。
「正社員として働いている同級生の友人がきっかけです。実際に働いている中でしか得られないような仕事への喜びと熱意、そして仕事をどうすればうまくこなせるか悩んでいる同級生の成長している姿を見て焦りを感じました。自分も正社員という責任のある社会人になり、人間として成長を遂げなければと思いました」
【既卒就活の質問例】4. 何か質問はありますか
いわゆる逆質問です。どう質問すればよいのかわからないという声も少なくありませんが、自分をアピールするチャンスでもあります。回答によっては、やる気や積極性、志望度の高さが見えて評価につながるため、企業研究を通じて質問を準備しておきましょう。
回答例
「御社でご活躍されている方に共通点などはございますか?」
「御社の〇〇部署について、強みや弱みなどを現場で働く方の観点から教えてください。」
既卒の就活がうまくいかないときの対処法

すでに述べてきたコツや注意点をもとに対策を講じても、就活がうまくいかない既卒者の方もいらっしゃると思われます。
そういった場合には下記のような対処を行ってみてください。
・前向きな気持ちを持つ
・周りの人に相談する
・何か行動してみる
・条件に優先順位を付ける
前向きな気持ちを持つ
既卒就活に対して辞めたい、つらいといったマイナスな気持ちを抱いていると、実際の面接などのやりとりで企業の採用担当者に自信のなさや意欲の低さが伝わってしまう可能性があります。前述したように目標とスケジュールを立て、就活に対して前向きに取り組むことが大切です。
それでも就活がうまくいかずに気持ちが落ち込んでしまうことはあるでしょう。
そういった場合には一度就活から離れて、気持ちをリフレッシュするのもよいかもしれません。
周りの人に相談する
就職活動に限らず、物事がうまくいかない場合には第三者に相談すると、ヒントがもらえて悩みの解決につながりやすくなります。周りの意見やアドバイスを取り入れて、モチベーションの維持につなげられるのはもちろん、実際の仕事内容を知ることで自分に合っているか考え直せることもあります。
初めての就活の場合は、そもそも何をすればよいかわからないので、友達や社会人の先輩に相談してみるのが最も効果的です。転職エージェントを活用して、一から手順を教えてサポートしてもらいながら就活を再開してみるのもよいかもしれません。
何か行動してみる
「いい会社がないから応募できない」となんとなく就活を先送りにすると、就職のタイミングを逃してしまいます。正社員として雇用され、社会で働きたいのであれば不安や悩みに向き合って早めに就活を始める必要があります。先に述べてきたように、明確な目標や期限を決めてから必要な行動を逆算して、週に1回は必ずエントリーするなどの具体的な行動に移すことが大切です。
条件に優先順位を付ける
上記の「何か行動してみる」とはまた別に、具体的な目標や働くための条件を厳しくしすぎてしまってはいけません。例えば「大手以外は論外」「この職種以外は無理」など、こだわりが強すぎるとそもそも条件に合った求人自体が少なくなり、就活が難しくなります。そもそも人気の企業や職種は倍率が高いため、就活がうまくいかないときは条件に優先順位を付け、理想を高く持ちすぎないことが大切です。
既卒の就活によくある質問

ここでは既卒者の方が就職活動で気になる質問をまとめています。
・新卒と中途のどちらで応募すればよい?
・既卒でも大手企業への就職は狙える?
・企業が既卒者を採用する理由は?
・既卒におすすめの就活方法は?
・既卒者が就活を開始する時期はいつがいい?
上記のうちで気になる質問があれば、その回答とポイントをしっかりと押さえておきましょう。
新卒と中途のどちらで応募すればよい?
基本的には、新卒枠と中途枠の両方に応募が可能です。しかし、企業によって新卒として取り扱う範囲が異なるため注意しましょう。
応募条件を満たしているか、あらかじめ採用サイトや求人サイトの詳細から確認しておくことが大切です。
新卒枠では新卒と違い空白期間の有無によるマイナスイメージといったデメリットや逆にその期間や経験を生かした資格取得といったメリットがあります。
中途枠では熱意やポテンシャルでの採用を図ってもらえるものの、経験やスキルにおいてはほかの応募者に差を付けられてしまいます。
両者メリット・デメリットがあるため、どちらの応募が向いているかしっかりと確認し対策しておきましょう。
既卒でも大手企業への就職は狙える?
募集人数が多ければ大手企業であっても既卒者が採用される可能性があります。ただし、新卒の方が選考に有利な傾向があるのは事実です。また、新卒のみを募集しており既卒は大手企業への応募自体が難しいこともあるため、中小企業も幅広く検討してみてください。
中小企業の求人を探すときはすでに述べたように、転職エージェントや友人の紹介、ハローワークなどを活用してみてください。
企業が既卒者を採用する理由は?
人材不足が一番に挙げられますが、「新卒採用で人材が集まりきらなかった」「若年層の人材を集めたい」といったように企業それぞれの理由があります。求める人物像にマッチしている若い人材を長期的に育成することで長く活躍してもらいたい、という企業側のニーズを読み取って自分自身の強みと接点をつなげることが既卒者の就活において大切なポイントとなっています。
既卒におすすめの就活方法は?
転職エージェントの活用がおすすめです。転職エージェントは個別にキャリアアドバイザーがつき、綿密に話し合うことで希望する条件を言語化するところから求人の紹介、書類準備や応募先企業に応じた選考対策などを的確にサポートしてもらえます。転職サイトでは既卒者自身で求人を探して応募し、自分自身で就活を進める必要があるため自分から行動するのが苦手な方にはあまりおすすめできません。新卒応援ハローワークは転職エージェントと同様のサービスを誰でも無料で受けられる一方で、インセンティブといった追加報酬がないため相談員の熱意が転職エージェントと比較して少ない場合があります。しっかりと支援を受けて希望に沿った就職を実現するなら転職エージェントの方がおすすめです。
既卒者で初めて就活をする方にも転職エージェントはご利用可能です、ぜひ検討してみてください。
既卒者が就活を開始する時期はいつがいい?
思い立ったらすぐに始めるのがベストです。既卒者は年齢を重ねるにつれて新卒採用枠で応募可能な求人は減っていき、既卒という枠組みを過ぎると中途採用枠での応募しかできなくなっていきます。そうなると社会人として実績を積んでいるほかの応募者の方がライバルとして増えていくため、リスクが一番少ない早めの時期にスタートしましょう。
既卒の就活ならジョバディにお任せ!
学校を卒業してから1~3年経った、一度も就職をしていない既卒の方でもコツを押さえておけば就活を成功させることが可能です。ただし、魅力的なアピールの作成や既卒歓迎の求人を探すのは難しく、そのためには相談しながらサポートを受けられる転職エージェントを活用するのがおすすめです。
既卒の就職活動に不安がある方はジョバディを利用してみてください。
ジョバディはキャリアアドバイザーが多数在籍している転職サービスです。
最初から最後までのサポートはもちろん、必要に応じた部分的なサポートも得意としております。
もちろん書類選考をより通りやすくするための職務経歴書などのチェックや添削も可能です。
下記URLからまずはサービスの概要を見て、気になった方や転職に不安がある方はご利用登録されてみてはいかがでしょうか。
ジョバディのココが「ちょうどいい!」:https://jobuddy.jp/about
転職にいいこと、まるごと。jobuddy+:https://conciermatch.work/
ジョバディの使い方:https://jobuddy.jp/howtouse